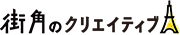時間と記憶、それから恋愛
平野啓一郎はどんな作家か? を語るとき、どうしてもややこしい説明が必要だった。投稿によってデビューをした異色の経緯をもつ作家であること。「個人」の対になる概念として、「分人」という考え方を提唱していること。私小説に対する距離のとり方、メディアコンシャスなあり方・・・。とにかく、1つ1つの要素が重要だから、説明するのが怖いのだ。
『マチネの終わりに』を読むまで、わたしは平野啓一郎のことを「マジでやばい」とか「分人のひと」とか、雑すぎる説明で逃げてきた。しかし本作を読んで、1つの答えを得たと思う。平野啓一郎は、出来事を予感として描き出す作家である、と。
洋子に出会った主人公・蒔野は、考え続ける。再会するまでの時間の中で、2人の行く末を様々に予感する。未来を手繰り寄せようとするのだ。それも、切ないほど冷静に。まだ、具体的なものごとが立ち上がってはいない。けれども恋は始まっている。私は最初の3章を読んで
マチネの終わりに始まるのは静寂だ。だが私たちがひとたび空間に耳を澄ませさえすれば、静寂の向こうから無数の聴衆の、そしてプレイヤーたちの、生々しい息遣いが聞こえてくるだろう。