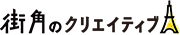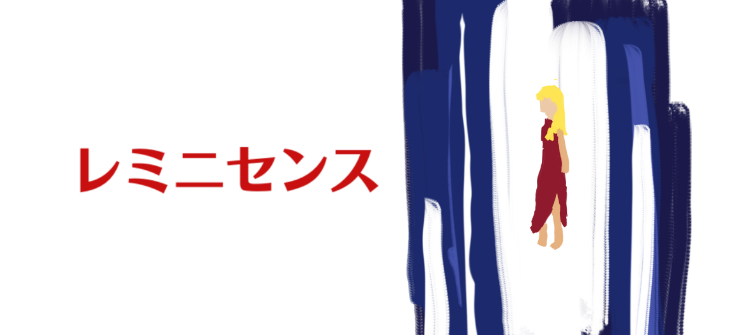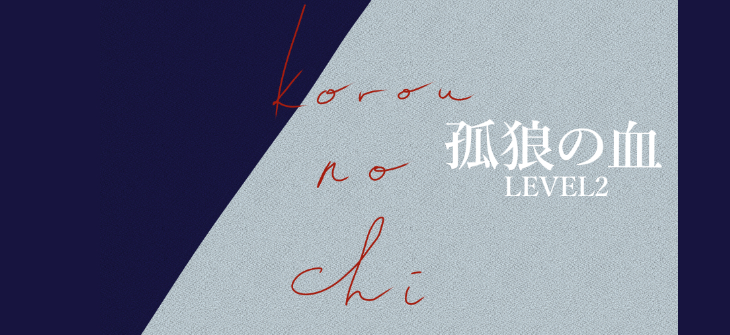もう、「最後の決闘裁判」について何か書くことは、なんだか陪審員裁判に被告として立たされているような気がしてならない。本作は絶賛から酷評、あるいは「ちょっと微妙」まで、さまざまなグラデーションの感想・批評が溢れている。
しかも#MeTooをかなり意識して制作されているので、下手を打ったらとんでもないことになる可能性すらある。事実、どえらいことになっているプロの映画批評家の方も居た。あれは仕方ないと思うが。
そんななか、徒手空拳で映画評を書くのはおっそろしいのだが、率直な感想をまず述べるならば「映像や音響、演出などは素晴らしいんだけど、事件の描き方や、マルグリットの扱いは正直ちょっと……さぁ……」といった感じだ。以下、本作の良かった点をはじめ、何が「ちょっと……さぁ……」なのかを掘り下げていきたい。
映像と音響はとにかく素晴らしい。映画館で観るべき作品だといえる

出典:映画.com
まず、映像と音響はとにかく素晴らしい。画面の隅から隅まで完璧で、平民はとにかく汚く、貴族もたまに汚い。もちろん騎士も汚い。そして人と同じくらい登場する牛や馬、アヒル(鶏だったかもしれない)の密度は「最後の決闘裁判」が東京都世田谷区だとしたら、同じく公開中の「DUNE」が北海道中標津に感じてしまうほどの密度差で、いろんな人やモノがこれでもかと映し出される。たぶん白黒上映したらキレイな「神々のたそがれ」くらいのインパクトにはなるんじゃないだろうか。
音響技術に関しては、たとえば街のシーンであれば、馬の蹄の音、鍛冶屋で剣を研ぐ音、家畜の鳴き声、人々の声、何かと何かがぶつかる音、つまりありとあらゆる生活音が過不足なく絶妙に整音されている。とくに馬の蹄の音は大げさに感じる人もいるかもしれないが、あれば結構リアルで、地鳴りが近づいてくるかのような迫力に思わず東京競馬場の直線を思い出さずには居られない。
また劇伴も素晴らしく、全編通してケルティックな「北欧風」の楽曲が壮大にならされる。「フランスなのになんで北欧?」となるかもしれないが、主人公の1人であるジャン・ド・カルージュ(マット・デイモン)の祖先はノルマン人である。
演出も素晴らしいが、別に「羅生門」ではない

出典:映画.com
本作は3章構成となっており、中世フランスで起きたある「事件」をめぐる話となっている。
第1章はジャン・ド・カルージュ(マット・デイモン)の視点、第2章はジャック・ル・グリ(アダム・ドライヴァー)の視点、そして第3章はマルグリット・ド・カルージュ(ジョディ・カマー)の視点から描かれる。
カルージュはマルグリットの旦那であり、彼が城を留守にしている間にル・グリがマルグリットをレイプする。マルグリットはカルージュに暴行の事実を打ち明け、裁決は決闘裁判までもつれ込む。
それぞれの章では、ほぼ同じシーンが映し出されることが多く、カメラワーク、語勢などの違いで「異なる視点」を描いている。少しの演出の違いで全く違った印象にさせる手腕は「さすがリドリー・スコットですなぁ」と感心してしまうし、「映画の(演出の)面白さ」を改めて噛みしめることができる。このあたりの匙加減は唸らんばかりの巧さだ。
ところで「決闘裁判」と聞くと、まるで侮辱されて貶された名誉を守るべく行われる「決闘」をイメージしてしまうかもしれないが、実はそうではなく、フランス国王に上訴し「当事者のどちらが偽誓をしたか」を決定する正式な法的手続きである。
とはいえ、いきなり「決闘だ」「殺りましょう」となるわけではなく、刑事裁判の場合はその前に君主の裁きがくだされる。その裁決に不服を感じた貴族たちの最後の頼みの綱が「決闘裁判」であった。決闘裁判が行われる前にも、是非を検討する審問会がある。
本作においても、ル・グリを寵愛していたピエール伯(ベン・アフレック)によって無罪の判決がくだるも、カルージュはそれを見越して決闘裁判に訴える。
決闘裁判、及び本事件の顛末としては『最後の決闘裁判(エリック ジェイガー (著), 栗木 さつき (翻訳) 』にかなり詳しく書かれているので、気になる方はぜひお読みいただきたい。本作が「何を描いていないか」もよくわかる。
本作ではこの決闘裁判が行われるに至り、我々が抱いているような中世における決闘のロマンティシズムを相当程度打ち壊してくれるのも良い。もちろん過去と今を同じ目線で語ることはできないが、家柄・土地・金・権力・名誉欲など、さまざまな呪いに縛られている男たちの行動がいかにバカバカしいかをしっかりと描いている。
とはいえ、「ちょっと……さぁ……」といった点も多々ある

出典:映画.com
さて、三者三様で「誰が本当のことを言っているのかわからない(人によって異なる真実がある)」といった話になるかと思いきや、実はそうではなくレイプは厳然たる事実として描かれている。
「レイプは本当にあったのか、マルグリットが嘘を吐いているだけではないのか」といったレビューも散見されたが、これは完全に間違いだと思う。というか、どんな見方をしたらレイプがなかったことになるのだろうか。
で、このレイプシーンはル・グリの視点とマルグリットの視点で2回描かれるのだが、正直マルグリットのみでも良いと感じた。「マルグリット視点だけでは本当にレイプされたのかがわからない」という意見があるかもしれないし「2回やらんと(ル・グリの視点からも見せてやらないと)わからん奴もいるのだ」と言われれば、そんな馬鹿な人もいるのかと思いつつそうなのかもしれないが、逆に強姦犯の言い分に1章割くことにより、証言がすべて対等であるようにミスリードしてしまう人だっているかもしれない。
そして、筆者が決定的に「ちょっと……さぁ……」と思ってしまったのは、まさにこのシーンにある。書籍版『最後の決闘裁判』でのレイプシーンは映画よりも遥かにエグい。なにせル・グリだけではなく取り巻きのルヴェルも暴行に参加している(正確には、アシストしている)。あまつさえ、ル・グリは帰り際に硬貨の入った袋をマルグリットに向かって投げつけさえもしている。
もちろん史実を完全にやる必要はないし、インティマシーコーディネーターのアドバイスも取り入れることにより、演出で必要なギリギリの線で描いたらしいが、「マルグリットがされたこと」を改変するのは、それこそセカンドレイプの類であり、数百年の後にマルグリットの精神を再び殺すことにはならないのか、といった疑問も残っており、端的に非常にもやもやする。
リドリー・スコットやマット・デイモン、アダム・ドライバー、ベン・アフレック、以下制作陣が「今、これを作るのだ、伝えるのだ」といった気概を持って本作を撮ったのは間違いないだろう。だが、「映画として成立させなければいけない」といったリドリー・スコットの都合のようなものも垣間見える。主演男優2人+ベン・アフレックはいずれも「演じて損しかない」役回りだが、演技の出来はどうあれ、これまた贖罪と言ってもやぶさかではない使命感、みたいなものがあるのではと感じてしまった。意気込みはもちろん買う。それでもだ。
インティマシーコーディネーターも入れたのに、ジョディ・カマーも傷跡を残しそうなほどのシーンを気丈に演じきったのに、あの傑作ながらも日本ではスクリーンにかからなかった『女流作家の罪と罰』のニコール・ホロフセナーを脚本家に迎えているというのに、結果として『最後の決闘裁判』は「男の贖罪」「仕事の都合」としか言いようのない、上から目線の臭いがスクリーンの中に漂っている気がしてならない。以上が素晴らしい作品であると思うのと同時に、「ちょっと……さぁ……」と感じている理由である。
—
このコラムについてみんなで語り合えるオンラインコミュニティ「街クリ映画部」会員募集中です。また、コラムの新着情報をオリジナルの編集後記とともにLINE@で無料配信中です。こちらから「友だち追加」をお願い致します。
[イラスト]清澤春香