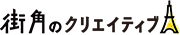文学史上、繰り返し書かれてきた「月」
タイトルにも用いられている「月」が、この物語の随所でキーとなる。繰り返すこと、把握できないこと、私たちの命の根源的な存在であること。月を扱った文学作品は過去にも多く存在している。ここで少し、紹介させていただきたい。
夏目漱石が「I love you」を「月が綺麗ですね」と訳した、という有名な逸話に見られるように、満ちては欠ける月の、捉えどころがない性質は、表現の世界において重要な要素であり続けた。
たとえば、狂気。“lunatic”という言葉が「月(luna)」というラテン語を含むことからも明らかだが、月は狂気――つまり、自分自身ではコントロールできないもの――の象徴である。
せっかくだから、まずは岩波文庫から一節を引こう。
1891年にパリで出版された、オスカー・ワイルドの戯曲『サロメ』。新約聖書を元にした作品である。王様から「ダンスを踊った返礼に何が欲しい?」と問われ、自分の愛を拒んだ予言者ヨカナーンを指し、「あの人の首をおくれ」と答えた王女サロメ。
「あの人と絶対キスするもんね」という宣言を、「あの人」の首を
彼女は物語の冒頭で、「月を見るのは素敵」と口走っている。また、この作品では以下のようなセリフが登場する。
さうだ、おれには解つてゐたのだ、月が
屍 を求めてゐたことは
(中略)
あゝ! なぜおれはこの男を月から隠してやらなかつたのだ?
引用:オスカー・ワイルド『サロメ』(1959)岩波文庫、p.37
悲劇の象徴としての月だ。こうした存在を恐怖する心は、人に、石を投げさせたりもする。未来派文学者であり少年愛のカリスマ作家でもある稲垣足穂は、こう書いた。
「今夜もぶら下がっていやがる」
石を投げるとカチン!
「あ痛た 待て!――」
お月様は地に飛び降りて追っかけてきた ぼくは逃げた
引用:稲垣足穂『一千一秒物語』(1969)新潮社、p.10
執念深い月は、夢の中まで追いかけてくる。うなされるのは、アヴァンギャルド文学の第一人者、安部公房だ。
たとえば、何度も繰り返し見た、いちばんなじみ深い夢は、ぼくの場合、笑う月に追いかけられる夢だ。最初はたしか、小学生の頃だったと思う。恐怖のあまり、しばらくは、夜になって
睡 らなければならないのが苦痛だったほどだ。
引用:安部公房『笑う月』(1976)新潮社、p.17
追いかけてくる、笑う月。砂の女もびっくりの不気味さである。はるか頭上に君臨する存在は、神様にもたとえられる。80年代半ば、アメリカ現代文学界で大いに脚光を浴びたポール・オースターは、月に重層的なイメージを投影した。
突然文字は消え、Moonのooだけが残った。そして、一方のoからぶら下がっている僕自身の姿が見えた。(中略)二つのoはいつしか目玉に変わっていた。二つの巨大な人の目が、蔑むように、苛立たしげに、僕を見下ろしていた。(中略)やがて僕は、あれは神の目なのだと確信するに至った。
引用:ポール・オースター『ムーン・パレス』(1994)新潮社、p.106
何をするでもなく、ただひたすらに、まざなしを与える神としての月が提示された。それは「僕」の精神状態によって、恐ろしいものにも、赦しを与えてくれるものにもなる。こうした「神の目」と共にあるのは、死者の存在だ。
月の光が照つてゐた
月の光が照つてゐたお庭の隅の
草叢 に
隠れてゐるのは死んだ児だ(中略)
森の中では死んだ児が
蛍のやうに蹲 んでる
引用:中原中也「月の光 その一」「月の光 その二」『汚れつちまつた悲しみに……』(1991)集英社、p.161、164
満ちては欠ける月のイメージが、灯っては消えゆく蛍のイメージと重ねられ、その揺らぎはさらに、命そのものの儚さとして昇華される。庭の隅に隠れているのはおそらく、二歳で他界してしまった中原中也の息子だ。生者が死者を思う時、そこにはただ月光がある。
この詩と同じく『月の光』というタイトルで小説を書いたのは、疾走感のある作風で多くのファンを持つ芥川賞作家・花村萬月だ。
神秘は月の光のようなものだ。狂気を孕んではいるが、それは人の心の奥底に秘めやかな
音叉 のように響いて、うつむき加減の心をやさしく愛撫するように慰めるものだ。(中略)俺は月の光を浴びるときこそ自立していたいと思うんだ。夜は決して負の世界ではない。マイナスではない。人は夜、歩くべきだ。
引用:花村萬月『月の光』(2002)文藝春秋、p.113
ここにきて、ある姿勢が示された。アンビヴァレンスであること(=月)に飲み込まれるのではなく、受け入れる。だがそれは途方もなく孤独な作業だ。孤独を受け入れることで初めて、人と繋がることができる領域が存在するのかもしれない。そのことを書いたのが、佐藤正午『月の満ち欠け』だった。
「神様がね、この世に誕生した最初の男女に、二種類の死に方を選ばせたの。ひとつは樹木のように、死んで種子を残す道。もうひとつは、月のように、死んでも何回も生まれ変わる道」
(中略)
「もしもあたしに選択権があるなら、月のように死ぬほうを選ぶよ」
引用:佐藤正午『月の満ち欠け』(2017)岩波書店、p.149
そう、『月の満ち欠け』は、生まれ変わりの物語だ。