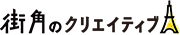「私」はもう死んでいる
そもそも、第1部2章のタイトル「みんな月に行ってしまうかもしれない」が「お星さまになっちゃった」的なレトリックである。この章で、主人公は仕事先(肖像画を扱うエージェンシー)に電話をするのだが、「交通事故にあったとかなんとか、先方にはうまく言っておいてくれませんか」(第1部、P.41)と言っている。そして携帯電話を川に捨て、橋を渡る。死んでるやろこれ。
こいつが死んでいる証拠はまだある。「私」はフラれた直後、1ヶ月半以上かけて新潟や北海道を旅行する(四十九日ともとれる箇所だ)。この旅は「あらゆる意味において急ぎの旅ではない」(第1部、P.40)。「急ぐ」というキーワードに関連して、村上春樹の他作品には、こんなセリフがある。
死んだ人間のことなら急いで考えることはないよ。大丈夫、ずっと死んでる。もう少し元気になってからゆっくりと考えればいい。
引用:『ダンス・ダンス・ダンス』下巻(村上春樹(1991)講談社)P.32
いやーやっぱ死んでますよね。考えてみれば、「あらゆる意味において急ぐ必要がない人間」なんて、そうそういない。時間と共に老いる存在である我々が、急ぐという行為から完全に自由になるのは難しい。そういう人がいるとすれば俗世を捨てた修行僧か、死者だろう。
旅の終盤で「私」は突然、回想を始める。「
さらに世界がねじれる:「私」はもう死んでいる、あるいは?
主人公が死んでいるとして、もう少し世界設定の話を続けてみよう。
旅を終えた「私」は、妻に電話を掛ける。そして「ぼくは生きている」「死んだのは車」だと言う。妻はこれに返事をしないが、すぐ後の別のやりとりの中で「どちらでもいい」という言葉を放っている。「鏡で見る自分は、ただの物理的な反射に過ぎない」とも言う。この会話を終えた主人公は鏡を覗き込み、そこに映っていた自分の顔を「二つに枝分かれしてしまった」「選択しなかったほうの自分」だと感じる。
ここで、世界がねじれている。今まで鼻息荒く「死んだ」「はい主人公死んだー」と得意顔になって読んでいた私のような読者に対し、忠告がなされたのだ。死んだのが「私」なのか「車」なのか、本当は「どちらでもいい」んだよ。この小説の中では、生と死が簡単に入れ替わったり二重写しになったりするんだよ、と。安易な解釈をするんじゃねーぞと釘をさされたわけだ。ほんと怖い、村上春樹。
はい訂正します。「私」はもう死んでいる。あるいは、まだ生まれていない。