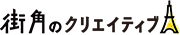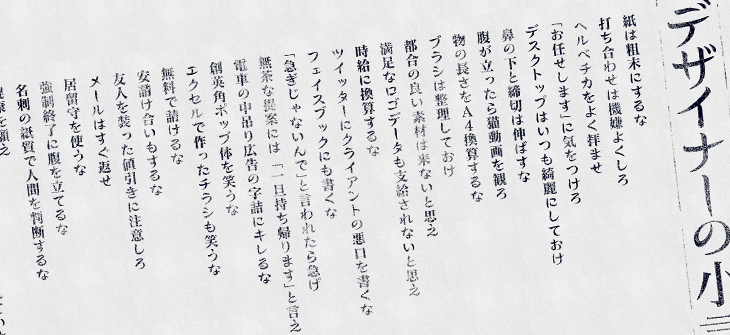結構昔、右の頬に51✕91mmほどの名刺サイズのこぶがあるおじいさんがいた。頬のこぶはよく見るとエンボス加工のようでもあり、角度を変えればデボス加工のようでもあり、つまりはぼこぼこしていて、率直な感想としては非常に気色悪いものだった。
おじいさんは、右頬にプリントされたこぶのせいで幼少時より迫害、差別されたがため、友人も出来ず、休日などは日がな本を読んだり、映画を観たり、パソコンを弄って架空の映画のポスターなどを制作したりしながら、日々を過ごしていた。薄暗いけれども、美しいものに囲まれた青春時代だった。
その後、幸か不幸かその文化的な生活が功を奏し、なんとか都会のデザイン事務所に就職した。
しかし、その醜いこぶのお陰で同僚からは差別され、飲み会にも呼ばれず、不遇な日々と人間の限界を超えたデス・ワークに心身ともに疲弊し、「あ、死のうかな」と思っていたところ、休日にたまたまネットで読んだ『まだ都会で消耗してるの?』というブログに感銘を受け、勢い会社を辞め田舎暮らしをはじめてかれこれ数十年、山に入ってクラウドソーシングで低単価の案件を受けつつ暮らしていた。
その日も朝からA4フライヤー両面デザイン、裏表合わせて8,000円(税・手数料込み)の案件から大量の修正、追加、差し替え、明日まで、などという注文が入り、「あ、あと社長の顔を笑顔に変えてください」と割りと無理めなご指示が書かれたメールをそっと閉じ、気分転換をしようと麓のコワーキングスペースまで降りていくところだった。
「さすがに笑顔にするのは無理だな。しかめっ面だったし」と思いながら山道を歩いていると、そのうち雨が降ってきた。「帰ろうかな、でも、今月行ってないから会費がもったいないしな」と考えながら小走りに進んでいたところ、小石に躓き転倒、「うわぁー」と叫びながらゴロゴロ転がり崖から滑落、遠のく意識のなかで「あと、もうひとつなんですが、枠の赤をもう少しフレッシュな感じにしてもらえます?」と書かれたメールが脳裏に浮かび、目の前が真っ赤になって気絶した。
「キンコーズ・・・キンコーズ・・・」どこからか聞こえてきた鳥の鳴き声でおじいさんは目を覚ました。雨は山全体を殴るように、一層強く降っている。全身が痛い。
なんとか身体を起こし、辺りを見回すと、近くに洞窟、というよりちょっとした窪みを発見し、雨宿りができそうだったので、身体を滑り込ませた。
「コワーキングスペース、やっぱり退会しようかな。こぶに対する視線も辛いし」と今後のことを考えながらしばらく過ごしていたのだが、雨が止む気配は一向にない。雨粒が、こぶに触れた。「このこぶもコンテンツに応じるで除去できたらなあ」誰も聞いていないのに、おじいさんはため息混じりに呟いた。
動けないまま、ああだこうだと考えているうちに、すっかり日が暮れた。辺りは一面の闇に包まれ、おじいさんは怖くて怖くて震えた。夜闇の色をCMYKで表すことを試みたり、窪みの縦幅をA4換算してだいたいの大きを想像してみたりと、何とか気を紛らわせようと努力していた。
何時間くらい経っただろうか、とうとうおじいさんは気が狂いそうになり、足元に転がっている石を並べてカーニングをはじめた。そのとき、遠くから話し声と、こちらに近づいてくる足音が聞こえた。しかも大勢である。
「助かった」と思った。そして「力の限り叫ぼう。最近声を出してないから出るかな? まあいいや、それじゃ、たす!」と声を張り上げようとした刹那、おじいさんは踏みとどまった。どう考えても、この山奥に、こんな天候状態の日に、団体で歩いている輩など居ない筈だ、ということを思い出したからである。
「Amazonか」とも考えた。しかし、基本的にドライバーはひとりであるし、配送業者のトラックが通れるような道もない。だとすると、これはもう幻聴、もしくは怪異の類であると考えるのが妥当であろう。
正体不明の音は、わいわい、がやがや、どすどすと、こちらに向かって近づいてきた。おじいさんが潜む窪みの前には、ちょっとした茂みがあり、その向こうに開けただいたい354330pixel四方くらいの土地があった。大勢の声と足音は、そこで止まった。各々がガサゴソと音を立て、何かを取り出しているらしかった。いつの間にか雨もあがっていた。
おじいさんは茂みから音のする方を覗き込んだ。暗くてよく見えない。だが、次の瞬間、暗闇に数十のAppleマークが浮かび上がった。「MacBook Air(Early 2015)だ!」そう思う前に、おじいさんは驚愕した。
驚愕した理由は、大量のAppleマークを見たからではない。マークの反対側、ディスプレイの光で映しだされた集団の姿が、人ではなく、鬼だったからである。
鬼は車座になり、その中央に火が灯されて、その姿がくっきり浮かび上がったときも、再びおじいさんは驚愕した。鬼のレイアウトや色使いはぐちゃぐちゃで、鬼としてのトンマナすら守られていなかったからである。
ある鬼は、R110,G255,B255くらいの目がチカチカする水色をしているし、コピースタンプツールで目を8個に増やしたような鬼もいた。フラットデザインみたいにペラペラなやつもいれば、Photoshopにデフォルトで付帯しているパターンをそのまま貼り付けたような体表の鬼もいた。中には人間にそっくりな者もいて、スーツを着てネクタイを締めていたが、口以外のパーツが顔についていなかった。