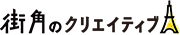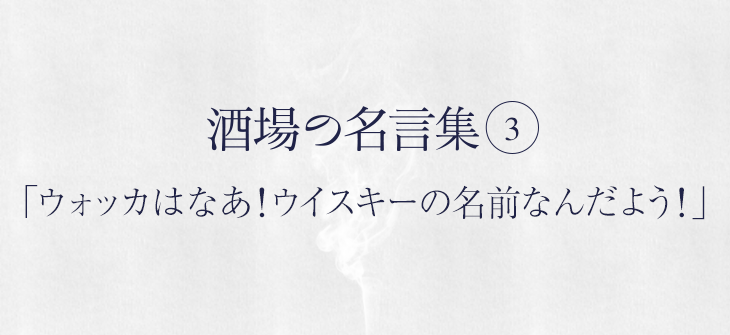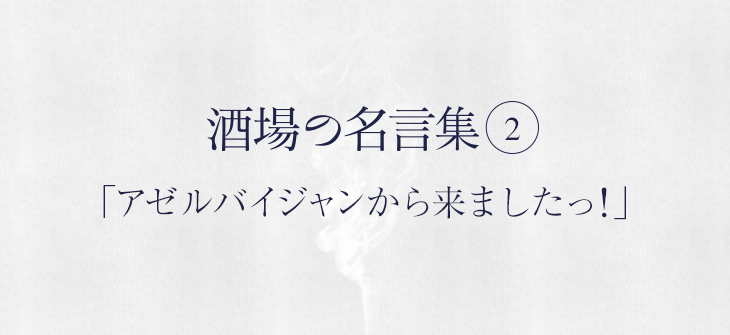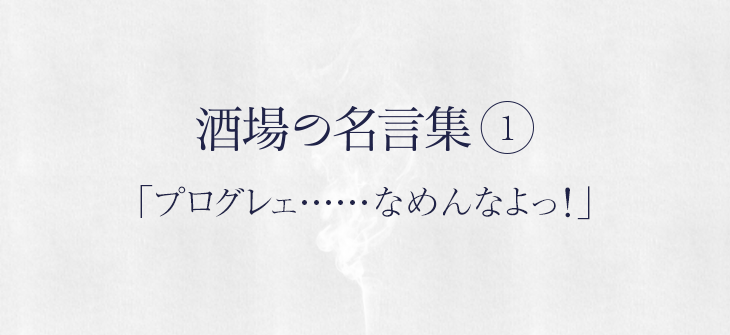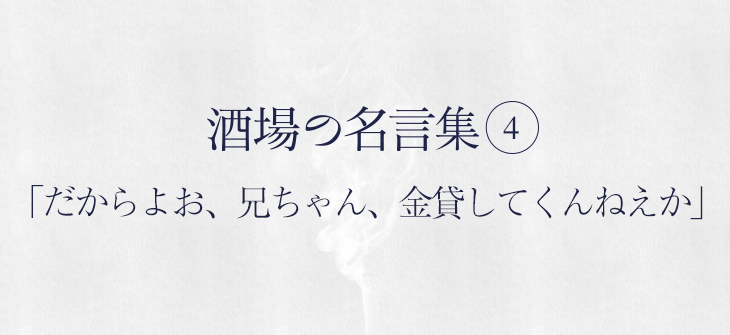
人は働いた対価として賃金を得て、家賃を払ったり米や野菜を購入したりする。そして時折、最低限の文化的生活を営むことが困難になり、消費者金融から当座の生活費を借りたり、家族、友人に金の無心をすることもある。ギャンブル狂の方々においては、生活費はおろか、勝負銭をそのような借金で調達しようとするケースも多い。
人間、手持ちの金が少なくなると心に余裕がなくなるもので、思慮に欠け、思いやりもなくなってしまうものである。時には、犯罪に走る者だっている。「長屋の花見」ではないが、人は煮出した番茶を酒に見立てて、大根のこうこをかまぼこに見立てて、陽気に宴会はできないのである。あれは、第三者の視点だから笑えるのだ。
さて、この話は前回も登場した渋谷の並木橋にある、場外馬券場の対面にある居酒屋で繰り広げられた一幕である。
その非常に年季の入った風通しの良いオープンな倒壊寸前の居酒屋は、その日も、ほどよく酔っ払ったおっさんと、結構酔っ払ったおっさんと、ぐでんぐでんに酔っ払ったおっさんの、主に3種類の人間が店内にひしめき、賑わっていた。コの字のカウンターの中でチャキチャキと働く、威勢の良い名物おばちゃんも、小気味良いグルーヴで店を切り盛りしていた。
俺はその日、二日酔いのうえに腹が空いていたので、カウンターに座るなり初来店以来ずっと気になっていた「モツ定食」なるものを注文した。まずモツ煮込みと飯で底を入れ、味噌汁で二日酔いを軽くいなして、香の物と余った煮込みで一杯やりながら競馬新聞を広げて予想をしようという算段である。
迎え酒として瓶ビールを頼み、タバコを吸いながら、道行く黒いダウンジャケットを着ているおっさんの数を数えていると、たいして間も置かずにおばちゃんが定食を運んできてくれた。
「はいよ! モツ定食ね!」
灰皿を脇にどけて、タバコの箱とライターをポケットにしまい、手渡されたトレイというかお盆を目の前に置いたところで異変に気付いた。
おかしい、モツ煮込みがない。今目の前にあるのは、白飯、味噌汁、香の物というより植物の欠片、そして得体の知れない串焼きが4本、タレもかからず無造作に置かれている。その横には、辛子らしき物体が申し訳無さそうにちょこんと頭を突き出して、非常にイエローな感じで発色していた。
「モツはモツでもこっちのモツですか」
と、軽く突っ込みながらも、これは参った。計画が崩れてしまった。口中は完全にモツ煮込みを受け入れる体制が整っている。しかし予想通りにいかなかったからと言って、このような労務者・博打打ち向けの店で文句を垂れ、「やっぱりモツ煮込み単品で……」と突っ返すなど、それこそ野暮天である。だが、どう考えても白飯とこのモツ焼きは絶対に相容れない。南無三、味噌汁を白飯に投入し、一気にかきこみ胃に下し、残ったモツ焼きで一杯やることにした。人生は常に軌道修正を迫られる。こんな場所でもだ。
「出汁」という概念が無い味噌汁は、二日酔いの頭にガンガンとキツいフックを入れてくる。口直しの、おそらく香の物であろう植物の欠片は、まさに“渋谷で食べられる野草”といった塩梅の味付けとルックスで、二日酔い特有の、頭を締め付けられているような痛みをさらに加速させた。口中に雪崩れ込む、そのマッシブ且つ塩分濃い目の味噌汁ご飯により、俺の味蕾が次々と死傷し、刻一刻と悪化していく状況は、まさにノルマンディ上陸作戦のオマハ・ビーチのようであった。
とはいえ、二日酔いの腹に何も入れずにこの店の酒を飲むのはさすがにまずい。確実にぶっ倒れるか、目が潰れるか、もしくはその両方になってしまう。
ちなみに、俺は人生で、他にここまで我慢して飯を食った経験は一度しかなかった。それは、小学校の給食で、「フルーツきんとん」という、ゲロの味がするオレンジ色になまめかしく光る物体を泣きながら食った時のことである。その時と同じく、今回も脳が、五臓六腑が、というか身体中が「もうやめてよお、お水が欲しいよお」と訴えてくるのであった。しかし、この店は水もヤバい。
なんとか味噌汁ご飯を食べきり一息ついたところで、さて、この目の前に鎮座するモツ焼きは果たしてどんなものだろうと、試しに一欠片食べてみた。すっかり冷えていた。というか、おそらく焼きっぱなしのものをそのまま、温めずに提供していた。
ゴムのようなモツ、噛み続ける俺、イエローに光る辛子、新聞紙の匂い、質の悪いアルコール臭、酔っぱらいの喧騒、灰色の空、きしむ長椅子、行き交うおっさんたち、誰かのラジオから聞こえてくる競馬中継のアナウンス……
薄れゆく意識の中、やっとのことでモツを喉に通したところで迎え酒のビールが少しだけ効いてきた。こうなればこっちのものである。おばちゃんにホットウーロンハイを頼み、競馬新聞を広げタバコに火をつけた。
さて、予想と頭痛も少し落ち着いたところで改めて辺りを見回してみると、この日もカウンターは、たくさんの酔っぱらいエリートたちがひしめいていた。
向かいの大柄なおっさんはずっと
「焼酎! 焼酎だよ! こ・れ・は・焼酎!」
と調子っぱずれに連呼し、おばちゃんに
「うるさいよ! もうあんた帰りな!」
と怒られている。
その隣には、口を近づけて飲みゃあいいのに手が震えていて酒がこぼれて飲めず、グラスをちょっと持ち上げてはカウンターに戻し、またちょっと持ち上げては戻しながら、悲しそうな顔をしているおっさん。
店の右奥には、極彩色の布に身を纏い、ひび割れだらけの白塗り化粧をした石化寸前のオカマを膝に乗せ
「なんぼやあ? なんぼやあ?」
と、なぜか関西弁で口説いている、だいぶお禿げ散らかしになられている中小企業社長風のおっさんもいた。
そして、俺の右隣には、中の羽毛が飛び出た黒いダウンジャケットを着たおっさんが、そのまた隣でコップを握りしめながら、うつむき加減で泣いているおっさんを慰めていた。
その泣いているおっさんは、蚊の鳴くような声で
「チクショウ……チクショウ……」
と繰り返しながら、ほろほろ涙を流している。
そして、隣の壊れたダウンジャケットを着用したおっさんは
「まあまあ、色々あるじゃねえかよ」
そう言いながら泣いているおっさんの肩を叩き、慰めていた。俺は「熱い友情だなあ、モツべきものは友達だなあ、モツだけに。なんつって」と思いながら、ホットウーロンハイという名前の、加熱した焼酎を飲みながら、2人の会話を小耳に挟みつつ、次のレースの予想をしていた。
5分ほど経った頃だろうか、ダウンジャケットのおっさんがぐるりとこちらに振り向き、いきなり俺に話しかけてきた。
「おおう、にいちゃんよう、コイツよお、馬券間違えて買っちまってよお、当たってりゃ100万だったんだってよお」
おっさんの目は焦点が合っていない、ついでに歯も2、3本無い。絶対に関わってはいけないタイプである。
「そりゃ災難でしたねえ……」
俺はそう答えて再び新聞に目をやったのだが、それがどうしたとばかりにおっさんの一方的なトークは続く。
「なあ、かわいそうだよなあ、にいちゃんいいやつだなあ。おれはよお、このおっちゃんを助けてやりてえのよ」
「はあ、そうなんですか。おじさんもいい人ですねえ」
と返したところで、「俺は、一体こんなところで何をしているんだろう」と正気に戻り、再び頭痛が襲ってきた。ウーロンハイが濃さを増した。結局、更に酔いが回った。
おっさんは構わず話を続ける。
「だろ、だからよお、おれはよお、このおっちゃんを助けてやりてえのよ、だからよお」
なぜか、もじもじし始めるおっさん。おっさんは文字通り“も”と“じ”のように、珍妙に身体をくねらせていた。これほどまでにもじもじしている人間を俺はこれまで見たことがない。もじもじもじもじもじもじもじもじとおっさんは動く、完璧なホラーである。そして、酔いも手伝ってか、おっさんが“も”とか“じ”という平仮名に見え始め、その平仮名がゲシュタルト崩壊を起こしそうになったその時、もじもじは最高潮に達し、頬を赤らめながらまるで中学生が意を決して告白するようにもじもじっと身体を震わせ、俺にこう言った。
「だからよお、兄ちゃん、金貸してくんねえか」
「もじもじが喋った!」
と、一瞬たじろいだが、幸い直ぐに正気に戻れた。こういう時ははっきりと断るべきである。思わせぶりな態度を取るのは非常によろしくない。酔った頭をフルスピードで回転させながら4文字の答えをはじき出した。
「いやです」
その時である。泣いていたおっさんがいきなり
「チクショウ……チクショォォ!」
と声を張り上げて立ち上がり、場外馬券場へとふらふらと歩き出し、道の真ん中で受身も取らずにぶっ倒れた。おっさんはピクリとも動かない。周りが騒然とするなか、すっ飛んで来た警備員に抱えられ、どこかへと消えて行った。あとから救急車が来ていたので、きっと病院にでも運ばれたのだろう。
騒動の後ふと横をみると、いつの間にか隣のおっさんはいなくなっていた。どさくさに紛れて無銭飲食をカマしたのである。あまりの手際の良さに、さすがのおばちゃんも「やられた」という表情で苦虫を噛み潰していた。
俺は、すっかり放置してあったモツ焼きをもう一欠片、噛み潰した。二日酔いの胃が、もじもじと動くのを感じた。