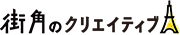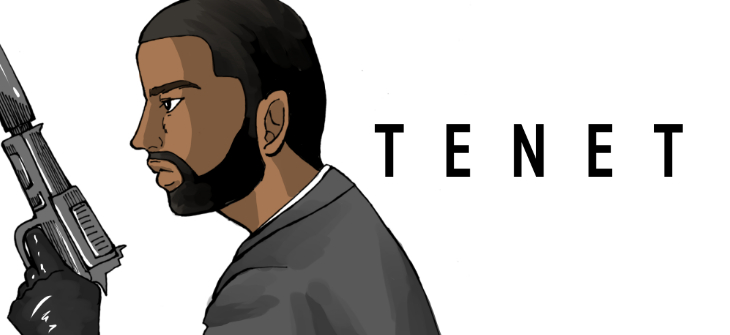ハリウッドを凄いと感じるのは、驚愕の予算や最先端CGではなく、自国の負の歴史を真正面から扱う作品に出会った時だ。
警官によって無実の黒人3人が射殺された1967年のアルジェル・モーテル事件を描いた「デトロイト」(2017)。実際に起きた女性キャスターへのセクハラ事件を映画化した「スキャンダル」(2019)。ベトナム反戦デモの参加者たちと司法が衝突する「シカゴ7裁判」(2020)などなど。挙げていけばきりがない。
映画には報道とは異なる役割がある。キャラクターとストーリーを通すことで、観客は事件を追体験できるのだ。劇場で大勢が観れば、社会全への影響も大きい。事件を総括し、忘却を防ぐことができる。
一方、邦画にこうした作品があまりに少ないことに、僕はずっと不満だった。硫黄島の戦いや水俣病までハリウッドに映画化されてしまう始末だ。
しかし、日本からも、すごい作品があらわれた。それが、さかはらあつし監督の「AGANAI地下鉄サリン事件と私」だ。

出典:eiga.com
オウム問題の終焉を目指した、たった1人の戦い
登場するのは、オウム真理教(現Aleph)の広報部長・荒木浩と、そのオウムが起こした地下鉄サリン事件の被害者である監督自身。しかし映画の内容は、オウムやAlephへの密着取材ではなく、2人が共通の出身地の丹波を旅する姿だ。カテゴリーとしてはドキュメンタリーだが、読後感はロードムービーに近い。監督自身が次のようにコメントしている。
—–
(前略)2012年から2013年にかけて私は四国一番札所の副住職(当時)に雇われ、お遍路の撮影旅行をしました。お遍路の途中、東京に所用で向かう飛行機の中で意識を失い、気づいたら腰椎の圧迫骨折をしており、京都の実家に戻りました。「私はいつまで生きているかわからない、生きている間に作るべき映画は何か」と考えてこの映画作りに向かい始めたのですが、お遍路は「発心」「修行」「菩薩」「涅槃」の四つの道場によって構成されていて「起」「承」「転」「結」を生み出す物語の半自動生成装置であると思ったのでその経験を参考にロードムービーを構想しました。私は学生時代からロードムービーの傑作『ミッドナイト・ラン』が好きだったのです。(出典:公式パンフレット)
—–
何も知らずに見れば、2人の関係が地下鉄サリン事件の被害者と加害者とは、とても思えない。にこやかに談笑して、川で石投げをして、イヤフォンを2つにわけて音楽を聴く。絵的にもデコボココンビ感があり、ほほえましい。

出典:eiga.com

出典:eiga.com
そんな印象から僕は本作を、オウムを理解しようとする、リベラルなスタンスの映画なのかと思っていた。「一方的なバッシングは何もうまない。わかりあおう」みたいな感じだ。
しかし、大間違いだった。「AGANAI」は、そんなヌルい映画では無かった。
被害者団体にも属さず、政治などの後ろ盾もない個人が、たった1人でオウムという歴史に残るテロ組織に戦いを挑んだ記録が、「AGANAI」という映画なのだ。
さかはら監督は本作公開に先立つ2021年2月に『地下鉄サリン事件20年 被害者の僕が話を聞きます』(株式会社dZERO)を出版している。地下鉄サリン事件当時、荒木氏と並んでオウムの顔として活躍した上祐史浩との対談本だ。

出典:ハフポスト
同書の中でさかはら監督はオウム問題の終焉を
1)麻原彰晃こと松本智津夫の死刑執行
2)(社会の受け入れ態勢の伴う)Alephの解散
3)(社会の受け入れ態勢の伴う)ひかりの輪の解散
4)真の被害者ケア
という4つがそろったときと定義している。
弁舌さわやかにマスコミに対峙し、仕事ができる男のオーラがあふれていた上祐氏は、一時期「上祐ギャル」という追っかけの女性が登場するほどの人気があった。現在は脱麻原を標榜する宗教団体「ひかりの輪」の代表をつとめている。(公安調査庁はAlephもひかりの輪も、いまだ麻原の影響下にある「国際テロ組織」と認定している)
また、上祐氏についてはこう記している。
——
「上祐史浩という人物」を物語として理解すると、「家庭環境、特に父との関係、父性の欠落を持つ男性が、出家して邪教に入信し、社会に多大な迷惑をかけた」という話です。ところで、物語とは何かというと「主人公が日常から非日常に出かけ(旅)、日常に戻ってくる。その非日常体験になんらかの学び、気づきがある」ということです。
(中略)
上祐史浩物語は「父性の欠落を持つ男性が、出家して邪教に入信し、社会に多大な迷惑をかけたが反省し、出家から社会に戻ってくる」という話でなければいけません。今、上祐さんは「ひかりの輪」という団体で活動されていますが、それはまだ「精神世界」「出家」の世界です。このことを私はオウム真理教の後継団体アレフの広報部長、かつての上祐さんの部下である荒木浩さんの取材中「上祐さんは結局、まだ出家していますね」という何気ない言葉から気づきました。
上祐さんには、社会に戻ってくる、社会の普通の世界に戻ってくるという作業をしてほしいと思います。ひかりの輪のメンバーであれ、元信者であれ、上祐さんが範となり、日常に連れ帰るのが責任の果たし方ではないでしょうか。
——
さかはら監督は「AGANAI」で、荒木氏を社会に連れて帰ろうとしているのだ。ともに故郷を旅し、出家前の若き日に思いを馳せる。この機に両親に会いにいくよう説得し、実現させてしまう。人懐っこい笑顔で接しながら、すべての言動が寸分の狂いもなく「荒木氏を社会に戻す」という一点に集約されていることがわかる。
荒木浩に見る「悪の陳腐さ」
荒木氏には失礼な書き方になるが、人間の厚みという点で、荒木氏はさかはら監督に全く歯が立たない。さかはら監督は友人の自殺をきっかけにアカデミー賞を獲ることを志し、地下鉄サリン事件に遭遇し、元オウム信者の女性と結婚・離婚し、プロデュースした短編映画がパルム・ドールを受賞し……という、監督自身の言葉を借りれば「一言では説明できない変わった人生を生きている」人だ。
一方、荒木氏は「子どもの頃、ずっと欲しかった筆箱を買ったものの、すぐに飽きてしまった」という経験を、俗世間を離れた原体験として語ってしまうような人なのだ。

出典:eiga.com
僕を含むほとんどの観客は、さかはら監督より荒木氏に近い凡人だ。さかはら監督が空海の三教指帰まで引用して、仏教知識においてすら荒木氏を圧倒してその信仰の矛盾をつく場面には、正直、恐怖すら感じる。
さかはら監督が、自分の両親を荒木氏に会わせる場面がある。被害者の両親を前にしても荒木氏は地下鉄サリン事件について、「麻原彰晃と幹部の村井秀夫が何も語っていない以上、真相はわからない」として、罪を認めようとしない。すると、さかはら監督は「サリン事件に会ったのは、自分がトンマだったからだと思っている。あの日、地下鉄に乗ったからだと。あなたには、言うべきことがあるんじゃないですか?」と荒木氏に詰め寄る。そして荒木氏はようやく、両親に謝罪の言葉を口にする。全編を通して、最大の見せ場だ。
「麻原や幹部が語らない以上、真相はわからない」というのは、事件直後から荒木氏が一貫して主張していることだ。これは嘘偽りのない、荒木氏の実感なのだろう。彼が上九一色村で出家生活に入ったのは地下鉄サリン事件の1年前。95年に事件が起きると「半ばなりゆきで、広報副部長に就任」(※公式サイトで、本人がこう書いている)している。当事者意識は薄いのかもしれない。
この「自分は責任者じゃない」というのは、組織的殺人にかかわった人間の言い訳のテンプレートであることは指摘しておきたい。このことを言及するとき、さかはら監督はトークショーで「悪の陳腐さ」という言葉を引用していた。
「悪の陳腐さ」とは、ナチスドイツのユダヤ人虐殺計画で主導的な役割を果たしたアイヒマンの裁判を傍聴した、ハンナ・アーレントの言葉だ。
—–
(前略)
このとき、連行されたアイヒマンの風貌を見て関係者は大きなショックを受けたらしい。それは彼があまりにも「普通の人」だったからです。アイヒマンを連行したモサドのスパイは、アイヒマンについて「ナチス親衛隊の中佐でユダヤ人虐殺計画を指揮したトップ」というプロファイルから「冷徹で屈強なゲルマンの戦士」を想像していたらしいのですが、実際の彼は小柄で気の弱そうな、ごく普通の人物だったのです。しかし裁判は、この「気の弱そうな人物」が犯した罪の数々を明らかにしていきます。
(中略)
アーレントがここで意図しているのは、われわれが「悪」についてもつ「普通ではない、何か特別なもの」という認識に対する揺さぶりです。アーレントは、アイヒマンが、ユダヤ民族に対する憎悪やヨーロッパ大陸に対する攻撃心といったものではなく、ただ純粋にナチス党で出世するために、与えられた任務を一生懸命にこなそうとして、この恐るべき犯罪を犯すに至った経緯を傍聴し、最終的にこのようにまとめています。曰く、
「悪とは、システムを無批判に受け入れることである」と。
(出典:東洋経済「9割の悪事を「教養がない凡人」が起こすワケ」)
—–
監督によれば、「AGANAI」というタイトルには「I(アイ)がない」という意味が込められている。
すべての日本人は、オウム問題の当事者だ
事件当時、麻原彰晃をはじめ信者たちの奇抜な言動にばかり注目が集まり、報道は異常な過熱ぶりを見せた。こうした状況を批判的にとらえたのが、森達也監督の「A」(1998年)だったと思う。森監督はオウム内部へと入り込み、外部へとカメラを向けた。そして、チンピラ同然のマスコミや警察の「転び公妨」など、僕たちが属している社会の異常さを赤裸々に映し出した。
しかし、26年が経った今、「A」のレビューに「オウムもひとつの宗教」「報道で誤解していたけど、良い人たち」という内容のものが増えていて愕然とする。そこには「悪の陳腐さ」への警戒心は微塵もない。
地下鉄サリン事件の被害者は、当時、その場にいあわせた人だけではない。テロというのは社会秩序の破壊であり、オウム真理教の攻撃対象は信者以外のすべての日本人だった。
この国で暮らすすべての人は、オウム問題の当事者なのだ。「麻原彰晃の心の闇は明かされなかった」みたいな定型文からは何もうまれない。記憶が風化しつつあるこそ、安全な場所から眺めるより、当事者として事件のことを考えたい。
そのための一歩として、まず被害者について考えることから始めようと思う。さかはら監督は、日本人はオウムには興味があるけど、被害者には興味がないとコメントしている。それが映画を撮った理由のひとつだった、と。日本人全員が被害者について考えるようになったとき、やっとオウム問題の終わりがはじまるのだと思う。本稿をここまで読んでくれたあなたにも、ぜひ「AGANAI」をひとつのきっかけとして、そうして欲しいと願っている。
2019年3月15日におきたニュージーランドでの乱射事件を受けて、アーダーン首相はこんなコメントを残している。(出典:BBC NEWS JAPAN)
「皆さんは、大勢の命を奪った男の名前ではなく、命を失った大勢の人たちの名前を語ってください。男はテロリストで、犯罪者で、過激派だ。私が言及するとき、あの男は無名のままで終る」
—
このコラムについてみんなで語り合えるオンラインコミュニティ「街クリ映画部」会員募集中です。また、コラムの新着情報をオリジナルの編集後記とともにLINE@で無料配信中です。こちらから「友だち追加」をお願い致します。
[イラスト]清澤春香