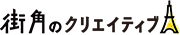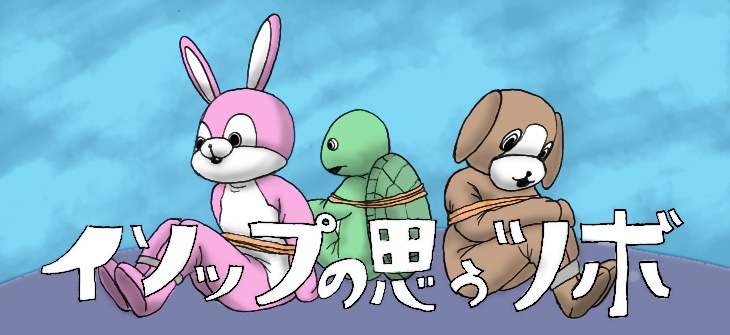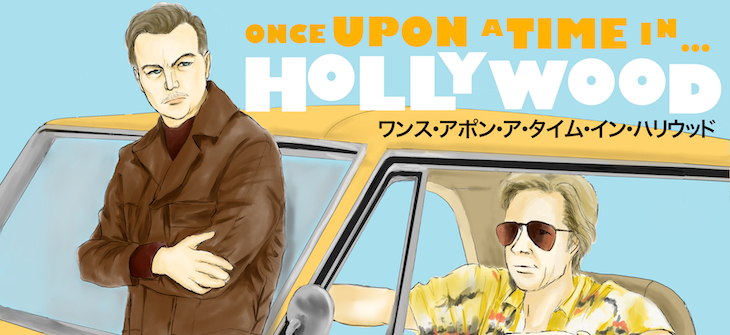
クエンティン・タランティーノはシネフィルであることを隠さないが、映画制作においての「正統派」な巧さは隠そうとする。が、その巧さは時折画面に表出してしまう。顕著な例が「イングロリアス・バスターズ」の冒頭であろう。タランティーノ流会話劇の極点とも言える凄まじいサスペンスと贅沢なカメラワークは、彼が映画巧者であることを如実に語る。
「ストリート上がりの悪童が、まるで正統派の才能ある映画作家に変わってしまったのでは」と懸念する我々に対して、タランティーノはすぐさま「お前ら安心しろ、いつもの俺だ」と言わんばかりに、ブラッド・ピッドが腕を組みながらナチス狩りの集団であるバスターズに向けて演説を打つシーンに切り替えてみせる。
彼は「イングロリアス・バスターズ」以降の「ジャンゴ 繋がれざる者」「ヘイトフル・エイト」において、自身のもはや隠し切れなくなった「巧さ」を、いかにして映画に組み込むかを考えていたように思える。
そして前作から4年後、ついに「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」が公開されたわけだが、結論から言うと傑作で、紛れもないタランティーノ作品でありながらも「巧さ」に対して的確に折り合いをつけている。
分子も、分母もタランティーノです

出典:IMDb
今まで隠していた「巧さ」をついに乗りこなしたタランティーノであるが、「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」では、「イングロリアス・バスターズ」で感じた「超絶技巧から一転、いつものタランティーノになる切り替わりの衝撃(あるいは笑撃)」を飛び越えて「安心して観ていられるけれども、今までのタランティーノとは何か違う。しかし同時に、めっちゃタランティーノ」という、ちょっとワケがわからない結果を生み出している。
このままでは書いている自分もワケがわからないので補足していくと、タランティーノは今まで数々の映画を分母として、分子がタランティーノ、つまり映画史分のタランティーノ史を作り上げていた。
「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」はインタビューや資料でも確認できるとおり、さまざまな映画や登場人物をモデルにしている。この点で分母は映画だが、彼の映画を分母とした作品群はやがて「タランティーノ的な映画」「タランティーノ的な会話」として、分母になるような1ジャンルを築いた。つまり、彼が分母とする映画には今や「タランティーノ」も入っている。
その点で本作は、分母もタランティーノ(成分多め)、分子もタランティーノといった具合で、今までのタランティーノ作品を彷彿とさせながら、更にレベルの高いタランティーノが乗っかる構造になっていて、要は数々の映画と同時に彼のフィルモグラフィも想起できるようになっている。これは前作まででもそうだったが、本作はより力が強い。この「強さ」はどこから出てくるのだろうか。
構造はよくある感じなのだが

出典:IMDb
本作の構造は単純で、1969年のハリウッドに架空の映画俳優リック・ダルトン(レオナルド・ディカプリオ)と彼のスタントマンであるクリフ・ブース(ブラッド・ピット)を投入。同年8月9日に起きた「シャロン・テート事件」に向けて話が進んでいく。つまり「イングロリアス・バスターズ」と同じく、歴史のなかに架空の登場人物を突っ込んで動かしていく手法がとられている。
「シャロン・テート事件」の話が出たのでついでに書くが、巷間で言われまくっているように、本作は当該事件について知らないと「それが起こってしまう日」に近づいていくサスペンスを味わえないし、彼女が送る「何気ない日常」がどれだけ尊いものかを感じることができない。
その点で、「この世界の片隅に」と構造が似ているともいえる。「原爆が投下される日」を知っているのと知らないのでは、劇中で描かれる「(戦時とはいえど)日常」がどれだけ素晴らしく、悲しいものかを感じることができない。
また、これまでの作品と比べると、タランティーノは観測者としての側面が強く出ているように思える。彼の再現した1969年のハリウッドは、映画産業やカルチャーが激変する最中においても美しいが、そこにはタランティーノ自身が「間に合わなかった」哀しみも漂う。当たり前だが1969年当時、7歳くらいだった彼は映画産業の中心には居ない。まるで小さな子どもがディズニーランドの外周(場所だけではない、写真や想像も含む)から内部を夢見るような描写だ。
再び映画を例に出すが、その点でディズニーランドの外周における貧困を描いた「フロリダ・プロジェクト」にも似ている。外周に住む子どもたちはディズニーランドには行けない。「何があるのかな」と想像するだけである。「フロリダ・プロジェクト」はラストでカメラがiPhone撮影に切り替わり、文字通り「中心」に突入していく。
「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」もまた、中心にシャロン・テート事件があり、外周を1969年のハリウッドや登場人物が取り囲む。タランティーノは映画のなかで時折「介入」してくるような描写をするが、これ以上はネタバレになるため書けない。
本作はまるでタランティーノが運転する車の助手席に乗り、「シャロン・テートはあの映画館で自分が出た作品を観るんだ。観客の反応を見て無邪気に嬉しがるんだよ」と、彼の解説つきで1969年のハリウッドをドライブしていくような感覚を覚える。実際調べてみたところ、タランティーノは1969年当時に義父の運転するカルマンギアに乗り、ロサンゼルスの街をドライブしていたそうだから、そこまで見当外れの意見でもないだろう。
夢のようなハリウッド。つまり、タランティーノが作り上げた1969年は完全な再現ではなく(ただ、時代考証はきちんとしているのでリアルさが損なわれることがない。)、彼の思い出や想像「きっとこうだったんだ(そうあって欲しい)」という願望、そして「間に合わなかった哀しみ」が混在している。そこでキャストを動かすことにより、胸を打つようなサウダージを生じさせる。舞台はより寓話的になり、まさに「ワンス・アポン・ア・タイム」をガッツリと補強する。
会話の質もよくある感じなのだが

出典:IMDb
劇中で繰り広げられる会話も、一聴するにいつものタランティーノである。延々と続く無駄話は彼の真骨頂でもあり、多くの模倣者を量産した。いわゆる「タランティーノっぽい会話」だ。
すでに指摘され尽くしているが、タランティーノ流無駄話の質は「イングロリアス・バスターズ」から少々変わった。具体的には物語に直接関わることを、さも無内容のように話させるということと、明らかに重要だと思われる台詞がわかりやすくなった。要は脚本が巧くなったのだが、功罪はさておくとして、本作はより顕著に出ている。
史実を基にした作品だし、スティーブ・マックイーンやブルース・リーなど実在した登場人物も多いので、当たり前といえば当たり前なのだが、クリフの名台詞「努力してる」などはタイミングを図ったようにと書いたが、むしろ明らかに図って繰り返される。
だが、本作における会話の白眉は「喋らせない」ことにある。タランティーノは意外と「何を言わせないか」にも長けているが、今回はシャロン・テート(マーゴット・ロビー)に対しての「喋らせなさ」が素晴らしい。タランティーノが用意した1969年の舞台のなかで、彼女はただ「生活」をするだけだ。パーティーに出かけて、音楽を聞いて踊り、友達と酒を飲む、子どもが生まれる準備をする。
喋らせ巧者なタランティーノがシャロン・テートを喋らせられないわけがない。「デス・プルーフ in グラインドハウス」のような女子会トークをしてもよかったわけだ。だが、タランティーノは鉄壁の抑制でもってそれをしない。彼はここでも観測者として振る舞う。タランティーノはまるで、自分の映画に銃なんて出したことが一度もないかのように、優しい眼差しをもってシャロン・テートを生き返らせ、生活させてみせる。
で、毎度人を喋らせすぎるタランティーノがあえて喋らせないのは、これはもう圧倒的な効果を生じさせる。正直な話、技巧云々よりも単純にズルい。
音楽もよくある感じなのだが

出典:IMDb
本作の音楽も、いわゆる「タランティーノっぽい」選曲で、ロールが去勢される前のロックンロールが鳴り続ける。サイケデリック方面に走り過ぎないのも好印象だった。
曲の使い方としては、割と劇伴をしっかりと鳴らしていた「イングロリアス・バスターズ」「ジャンゴ 繋がれざる者」「ヘイトフル・エイト」とは若干異なり「パルプ・フィクション」や「レザボア・ドッグス」に近い。会話や構造は「イングロリアス・バスターズ」以降を踏襲しつつも、セレクターとしては「デス・プルーフ in グラインドハウス」以前のような手法を用いることで、より分母も分子もタランティーノ感が出ている。
また、車のラジオから曲が流れている設定の場面が多いので、曲の途中でもガッツリとぶった斬っていく。ときにゴダールは「はなればなれに」で、フェードアウトを使用せず唐突に音楽を切っていたが、タランティーノも自身の流儀を守りながら、ラジオのチャンネルを変えるように音楽をブツ切りしてみせる。彼が作った映像制作会社「A Band Apart」は「はなればなれに」の英語読みであるが、今回のやり方は「音楽が好きで仕方ないゴダール」のようで興味深い。
個人的な判断になってしまって恐縮だが、本作でかかる曲で最も素晴らしいセレクトは、ローリング・ストーンズの「アウト・オブ・タイム」だ。ブツ切りされるトラックリストのなかでも、かなり長めの尺を割いて使われている。歌詞の訳し方によっては失恋ソングでもあり、時代遅れの奴、時代に乗り遅れた奴、チャンスを逃した奴に向けた歌ともとれる。
本曲がどのシーンで、いかなるタイミングでかかるかはネタバレになるので書けないが、タランティーノとしては珍しい音楽の使い方だと思う。劇中歌は時として登場人物の心情を表すのに使われるが、「アウト・オブ・タイム」は登場人物というよりも、タランティーノがリックやクリフなど、時代遅れの男たちに捧げた応援歌であり、そして最悪のタイミングで事件に遭ってしまったシャロンへ捧げる鎮魂歌だ。そして、1969年に「間に合わなかった」タランティーノ自身にも捧げられていると感じる。何度観てもグッときてしまう。
余談になるが、ブライアン・ジョーンズも1969年に死んだ。本作にブライアン・ジョーンズが登場する余地はないが、もしタランティーノが彼に対しても「アウト・オブ・タイム」を捧げていたとしたら、少しだけ嬉しい。
記号化もよくある感じなのだが

出典:IMDb
またまた「イングロリアス・バスターズ」以降になるが、タランティーノはナチスを記号化し、白人至上主義者を記号化し、まるで「お前らがファッションでカッコいいと思ってる奴らなんて、この程度の野暮天どもだぜ」と言わんばかりに徹底的に茶化してきた。今作ではマンソン・ファミリーが標的である。
是非は別として、これは非常にアメリカ的なやり方で、例えば米国は1915年にハイチを占領した後、芝居や映画などでゾンビを茶化してヴードゥーのイメージダウンを図ったことがある。他国の文化や宗教をシュガーコーティングしたり記号化したりして価値を下落させるのは、欧米がよくやる手口だ。ちなみにゾンビに関しては、幸か不幸かイメージダウン作戦のおかげで1920年代からプチゾンビブームが巻き起こり、現代にゾンビのごとくわらわらと溢れるゾンビ映画の礎となっている。
が、今回のマンソン・ファミリーは記号化などではない。ガンマンのようなタランティーノは明確な怒りをもって歴史と対峙している。彼らがどのような集団かは検索していただくとして、本作のマンソン一家はナチスよりも、KKKよりも異物感を伴って描写されている。
それがリアルかアンリアルかはさておき(本作に関して、存命中である元ファミリーからとったインタビューすらネットで読める)、必要以上の記号化はせず、それでいてタランティーノらしく落とし込む技術と怒りは凄まじい。例によってネタバレできないので詳細は記述しないが、誇張はあるにせよマンソン・ファミリーをある意味で「茶化しすぎない」ことにより、タランティーノはアメリカ的な病をも完治させた。
共通するのは会話と音楽

出典:IMDb
タランティーノがどんな映画を撮っているにしろ、ずっと共通しているのが「会話(無駄話)」と「音楽」であることに異論がある方は少ないだろう。本作も無駄話は続き、音楽は鳴り続ける。我々はタランティーノが作り上げた1969年を見つめながら、シャロン・テート事件の行く末を見守る。見守ることしかできないと言い換えてもいい。
ここからは少しだけ結末を想起できる文章になる。できるだけボヤかして書くが、それでもギリギリモザイクである。なので未見の方は飛ばして欲しい。
で、映画を観た人向けに書くが、タランティーノはいつだって、批評はどうあれ映画を、そして映画館の暗闇に紛れて鑑賞する者たちを信頼して映画を作り続けてきた。本作は、映画を観続けてきた者たちへのプレゼントであり、どうすることもできない喪失を抱えた人たちに対するギフトでもある。
世界では常に戦闘や復讐がおこなわれている。だが、タランティーノは現実世界において暴力も銃弾も、ミサイルも核爆弾も使わずに、映画作家として、これ以上ないやり方で1969年の8月9日にケリをつけた。こんな平和な解決方法、映画にしかできない。「これが映画の力だ」なんてクッセぇパンチラインを並べるのは死んでも嫌なのだが、でもやっぱり「映画の力」でしょう。
「ワンス・アポン・ア・タイム」は「昔むかし……」という意味だが、つまるところ「もしも話」である。例えば、我々がもう、この世に居なくなってしまった友人や家族に対して「もしも」を想像するとき、対象が本当に生きているような気がしてこないだろうか。
もう会えない人、もう一度会いたい人に対して「もしも」と想像するとき、私達は少しだけ喪失を和らげることができる。それは決して気休めではないし、現実から逃避するための嘘でもない。「心の中で生きている」なんてクリシェでもない。彼や彼女は確かに「もしもが実現した世界」に居るのだ。人類が並行宇宙だマルチバースだとやってるうちに、タランティーノは「アウト・オブ・タイム」なやり方を使い、「ワンス・アポン・ア・タイム」の一言でそれを証明した。
—
このコラムについてみんなで語り合えるオンラインコミュニティ「街クリ映画部」会員募集中です。また、コラムの新着情報をオリジナルの編集後記とともにLINE@で無料配信中です。こちらから「友だち追加」をお願い致します。
[イラスト]ダニエル