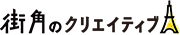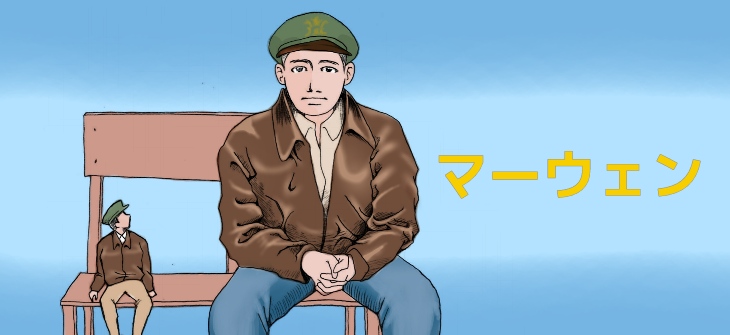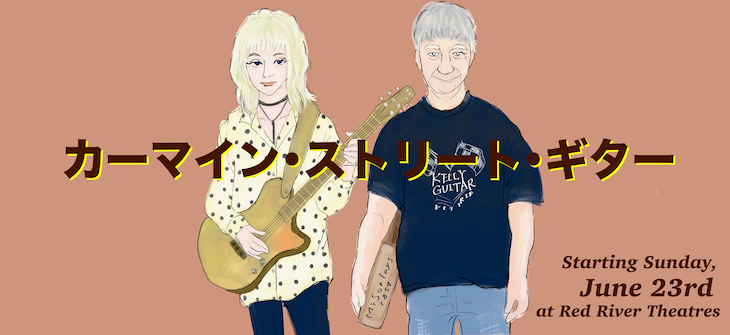
デザインでも、広告でも、音楽でも、映画でも、とにかく何でもかんでも直ぐに忘れ去られて新しいものが消費され続ける、流行り廃りのサイクルが加速し続ける現代で、時代の風雪に耐えうるような「忘れられない物」を作る価値はどれほどだろうか。その価値を提供できる者としては、優秀なクリエイターやアーティストだと考えるのが妥当なのかもしれないが、筆者の見積もりは若干違う。とにかく速度が要求される世の中で、我関せずと後世に残り続ける価値を提供できるのは(あらゆる業種に存在する)職人たちである。だが、残念ながら職人仕事は忘れ去られる以前に、多くの人に知られることがない。
職人の多くは口が悪く、というか口下手である。なので口では発信しない。むしろ発信する必要がない。自身の手による制作物が「発信」だからだ。さらに職人は大量生産ができないので、需要と供給がマッチングしてしまえば、それ以上の宣伝は不要である。つまり「食えればいい」ので、更なる露出や売上を求めない。職人の意識は「良質なモンを作り続ける」ツマミがフルテンになっている。後は蛸壺化するのみで、仕事に触れて感動した他者の手以外では拡散されることはない。
なので、あまり知られていない彼・彼女等の「いい仕事」を、仕事に関係の無い者に広く知らしめるためには、第三者の手が必要になる。その好例としては「ドキュメンタリー作品」が挙げられるだろう。職人側としては余計なお世話かもしれないが、「いい仕事」を観るのはとても楽しい。我々は数々の良質なドキュメンタリー作品でその快感を知ってしまっている。
本作「カーマイン・ストリート・ギター」もまた「いい仕事」をする職人を題材にしている。さらに、カメラは職人の仕事を単純に記録するだけではなく、職人たちの日常を適切に映し出す。
「カーマイン・ストリート・ギター」は、ニューヨークのグリニッジ・ヴィレッジにあるギター工房・ショップの名である

出典:IMDb
店主のリック・ケリーは時代のついた道具に囲まれた工房で、ニューヨークの古い建造物から出た木材を使ってギターを作成している。どこからどう見ても「職人」といった出で立ちのリックと背中合わせになるように、銀髪に近いブロンドの若い娘がスケッチを眺めている。目元にスーキャットウーマンのようなメイクを施したパンキッシュな彼女は、弟子のシンディ・ヒュレッジだ。
工房の外にはリックとシンディが作ったギターが陳列され、販売されている。リックの母であるドロシー・ケリーは、いかにも老人らしい、ゆっくりとした贅沢な動きでギターのホコリをハタキで落とす。店の電話が鳴ると受話器を手に取り、これまた老人特有の、ビブラートの効いた声で「カーマイン・ストリート・ギター」と応答する。
ニューヨークにあるギター工房兼ショップ、職人気質のギタービルダー、パンクスの弟子、チャーミングな老婆からなるキャスティングはまるで映画の世界だが、本作はドキュメンタリー映画だからして、「カーマイン・ストリート・ギター」は実在する。掲げた写真を参考にして欲しいが「ニューヨークのギター職人と、店に集まるミュージシャンの交流を描いた映画」と言われても何ら違和感がない。実際に本作は、脚本が存在しているかのように進行していく。
この手のドキュメンタリーとしては、店主や従業員などのインタビューや、顧客であるミュージシャンが、自身のスタジオや家で椅子に座りながらギターや店について話り、「カーマイン・ストリート・ギター」の全貌を、一枚の板からボディを削り出していくように語るのが通常のやり方であろう。
だが本作は、インタビューの類はおろか、登場人物のほとんどカメラ目線にすらならない。リックやシンディが来店したミュージシャンと会話をしたり、二人が工房で遣り取りをしたり、作業風景を映したりして話を進める方法をとっている。
なので、若干カメラを意識しているのがわかってしまうシーンもあれば、仕込みのミュージシャンが来店することもあるのだが、別に問題はない。「モノが確か」だからである。
テクニカルな話は無い。「好き」と「愛」が過不足なく鳴らされる
本作は、カーマイン・ストリート・ギター店の月曜日から金曜日までの5日間を記録している。毎朝リックが店を開けて、シンディとともに工房でギターを作ったり、来客対応をしたりするシーンが紡がれていく。つまり「日常」が映し出されているのだが、小さなギターショップの日常は滅法面白く、幸福に満ち溢れている。
ある1日では、パティ・スミスと長年バディを組んでいるレニー・ケイが店にふらっとやって来て、カウンターの中に立つリックと会話をはじめる。1969年のニューヨークや、ジミ・ヘンドリクスにまつわるやり取りは、まるで「スモーク」そのものである。
「スモーク」はブルックリンの街角にあるタバコ屋で繰り広げられる常連や飛び込みの客による無駄話が素晴らしかったが、「カーマイン・ストリート・ギター」では、現実世界で「スモーク」と同じような会話がなされている。店内で交わされるギター談義やニューヨークにまつわる話は、決して懐古趣味のような「あの頃はよかった」なんて話みたいに、鈍い光を放たない。都会の寓話のように語られる一つ一つの言葉は宝石のように輝きながら、半世紀前に時間が止まったような店内を飛び交う。
またある日には、お馴染みの髪型をしたジム・ジャームッシュが店の扉を開ける。本シーンに至っては完全に「ブルー・イン・ザ・フェイス」である。ジムは「このギターを見て欲しいんだ」などと言って背負っていたギターケースから竿を出し、リックと二人で木材のことや虫害について語り合う。彼は結局、世間話だけしてギターの弦を交換してもらい帰っていく。自分で弦を張り替えないジム・ジャームッシュ。繰り返すが、まるで映画である。

出典:IMDb
こうして「カーマイン・ストリート・ギター」の日常は過ぎていく。馬鹿みたいな表現になるが「好きなもの」について話している人間の顔や声は、本当に楽しそうだ。
楽しそうといえば、本作の白眉はおそらくドキュメンタリー史上最も贅沢な「試奏シーン」である。店に訪れたミュージシャンの手によるほぼフル尺の試奏は、スキルとギターの性能も相まって、とてつもない音を奏でる。
さらに彼・彼女等がギターを手にとったときに見せる驚きと嬉しさが混じり合った表情は、嘘が1%も混入していない。少年少女が初めてギターを持って、コードを鳴らした時のあの顔だ。リックのギターは百戦錬磨のミュージシャンであろうと、瞬時にギターキッズであった時代へと引き戻す呪術めいた力を持っている。
「(とんでもなく)いい仕事」から生み出されたものを体験するとき、人は思わず笑ってしまう。ギターでなくとも、信じられないほど美味いものを口に入れたり、驚くほど美しい革製品を手にとったときに「うわぁ、これ凄いな」と、思わず笑顔になってしまった経験がある方もいるはずだ。ちょうどあんな感じである。
リックとシンディ、そして客たちは、例外なく楽しそうにギターや木のこと、ニューヨークのことについて話し、生まれて初めてコードを鳴らしたギターキッズのように、嬉しそうにギターを弾く。「好きなものしかない世界」はある意味で地獄かもしれないが、「好きなものしかない空間」には幸福しか存在しない。
「スモーク」のような話が現実にあるという驚き、そして好きモン同士が集まるといった点で、本作はそこらの劇作よりもよほど健康的で幸福なヴァイブスに溢れていて感動するし、映画的であるともいえる。つまり映画とドキュメンタリーの中間的な立ち位置をとっているので、ギターに詳しくなくとも一本の映画として楽しめる。ドキュメンタリー映画は製作者の意図が必ず介入する(してしまう)が、本作はそれを隠そうとしない。明らかに意図的に作られているが、監督の意見みたいなものも表出してこないし「こんなこと、言わせたかったんでしょ」的な嫌らしさもない。
監督のロン・マンは「カーマイン・ストリート・ギター」を決して崇拝せず、適切なリスペクトをもってして「後に残るものを遺す」ことに徹している。その意味では、彼もまた職人である。
ちなみに、ギタービルドに関する技術的な話はほとんど出てこない。なのでテクニカルな内容を求めている方には物足りなさが残るかもしれない。筆者もその一人だが、これだけ誠実に「好き」と「愛」が過不足なく鳴らされる作品に、文句なんて言えようはずがない。というか「スモーク」の世界が現実で繰り広げられている時点で、そんなことはどうでもよろしい。
と、テクニカルタームがほとんど出てこない本作であるが
上述したとおり、リックはニューヨークの古い建造物から出た木材を使ってギターを作っている。「ニューヨークの歴史的建造物の木材を使って作られたギター」を弾くことは、街の歴史を弾くのと同義である。それだけで特別な一本であるが、彼のギターは「歴史ある木でギター作ってみた」みたいな安易な発想から作られてはいない。リックには200年以上前の木材を使う明確な理由と哲学がある。なので、ギターで最も重要なファクターである「音」と「弾きやすさ」も段違いで、圧倒的なオリジナリティがある。
ギターのオリジナリティに関しては、形は多様なものの、基本的なパーツや構造は変わらない。ボディがあってネックがあり、ピックアップがあり、中にはサーキットがある。これはジーンズの足が二本あるようなもんで、実用性とデザインを考慮すると、他と違うものを作るのは意外と難しい。
ではどうするか。繰り返しになるが、まず「ニューヨークの歴史的建造物の木材」を使う。加えて、リックは古い文献を紐解き、今では忘れ去られてしまったギタービルダーたちの技術を学び、制作に活かしている。この二点が「カーマイン・ストリート・ギター」のキモである。大手メーカーが作る大量生産品は、今ではほとんど個体差がないし、おそらく個体差が良しとされていない(所謂ヴィンテージギターやエフェクターに関する個体差に関しては、脇に置いて欲しい。今、凄くエレハモの話をしたいがそんな暇はない)。
だが、リックが作るモデルは先に記した二点により、明確な個体差が生まれる。古い木材と忘れ去られた技術を用いて、新しい一本を作る。まさに職人技である。手間がかかる割には儲からなさそうなのもまた職人っぽい。

出典:IMDb
リックは「考えるとすてきじゃないか、建築を支えた古材をギターに変えて、新たな生命を吹き込むなんて」「ギターを作ることは人生そのもの、ただ好きなんだ」と言い、シンディもまた「小さな工房だけど、こんな作り方しかしたくない」と、はにかみながら語る。物作りを生業にしている身で、これほど正直に、真っ直ぐに「好き」を表現できる人がどれだけいるだろうか。
ときに、ネット上では少し前に「好きなことで、生きていく」なんて言葉が飛び交っていたが、本当に好きなことで生きていく人というのは、リックやシンディのように、膨大な知識と智慧を持ち、とてつもない努力と工夫を日々重ねている人々のことである。
本作は「好きなものについて話し合う」ことや「物作りに向き合う姿勢」、そして、幸福な営為のためには「智慧」が必要だということを、木材を削る音や、楽しそうにギターについて話す声、素晴らしい試奏の音色をBGMに、大切に記録している。時代が止まったような小さなギターショップの幸せな日常が、変わらずに続いていくことを願わずにはいられない。
そんな時代遅れで愛すべき「カーマイン・ストリート・ギター」だが、実はInstagramをやっている。投稿担当はシンディだ。彼女は悪戯っぽくリックに尋ねる。
「携帯もインターネットもやらないなんて、そろそろ21世紀に来たら?」
リックは振り向かずに一言、答える。
「何のために?」
筆者はここで落涙した。スマホやネットの中に智慧は無い。賢者はストリートに居る。
—
このコラムについてみんなで語り合えるオンラインコミュニティ「街クリ映画部」会員募集中です。また、コラムの新着情報をオリジナルの編集後記とともにLINE@で無料配信中です。こちらから「友だち追加」をお願い致します。
[イラスト]ダニエル