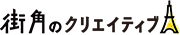美しく紅葉した木々が画面を彩るなか、道を歩くカップルをカメラが捉える。女は薄黄色のコートを羽織り、男はデニムジャケットのインナーの差し色に、彼女と同じ黄色を使っている。石造りのテラスのような場所に出ると、二人は幸せそうに見つめ合い、額をあわせる。
直後、同じように向かい合った二人の額の間には薄いガラス板が挟まることとなる。その薄さは見かけだけで、実質の距離はとてつもなく遠い。男はレイプ犯として逮捕され、冤罪であるというのに投獄されてしまったからである。
ガラス板の向こうで受話器を持った彼女は告白する。
「妊娠したの」
黒人が登場する(とくに1970年代を舞台とした)映画としては珍しく、高級メゾンのランウェイでモデルがテキスタイルを見せつけるかのように、ゆっくりと歩くようなテンポで、完璧な導入は完了する。恐ろしいまでの美しさ。本作が「バリー・ジェンキンスの新作であること」は、このオープニングを観れば一発でわかる。
ところで皆さんどうでしたか? 第91回アカデミー賞
第91回アカデミー賞は「グリーンブック」が作品賞を受賞し、助演男優賞・脚本賞と合計3冠を達成。「ボヘミアン・ラプソディ」「ブラック・クランズマン」「ROMA/ローマ」なども各賞を受賞し、ブラック・移民パワーはまだまだお強いですなあといった具合で、正直なところちょっと忖度し過ぎじゃないですかね、といった感想なのだが別にディスっているわけではない。
「グリーンブック」の監督であるピーター・ファレリーは「本作は最初から最後まで愛情についての物語だ。どんな違いがあたとしても互いに愛し合うこと、自分が何者かを知ること、私達は同じ人間なのだから」と延べ、「ボヘミアン・ラプソディ」でフレディ・マーキュリーを演じたラミ・マレックは自分がエジプト移民の子であるということや、アイデンティティーについて語った。
また、「ブラック・パンサー」の衣装デザイナー、ルス・E・カーターはアフリカ人の気品が、そして映画内の物語において女性が主導権を握る力を得たことが誇らしいと語った。長編アニメ部門を受賞した「スパイダーマン:スパイダーバース」の制作陣は、白人以外の映画好きが自分との共通点を見つけてくれるような映画を作ったと考えていると述べた。
ほかにもSNSで話題になったスパイク・リーのスピーチは言わずもがなだが、本作「ビール・ストリートの恋人たち」もレジーナ・キングが助演女優賞を手にした。監督は2年前の覇者、バリー・ジェンキンスである。

出典:IMDb
では「第91回アカデミー賞受賞。監督はあの「ムーンライト」で作品賞を受賞したバリー・ジェンキンス」といった触れ込みも可能な本作の公開規模はいかほどか。東京都内は4館だけだ。筆者が鑑賞したのは公開から10日ほど経ってからだが、すでに上映は1日1回となっていた。スクリーンも小さい。いっぽう、「黒人差別の問題を描いた」作品として共通する「グリーンブック」の公開館は受賞後も含めるが20を超える。スクリーンもデカい。
別に「差別を描いた映画同士を公開館数で差別するとは何事か! 全世界の感想が指先一つですぐに確認できる今、作品賞の権威なんてナンボのもんだよ!」とかアホなことを言っているわけではない。配給会社の力もあるし、劇場だって商売でやってるんだから仕方ないといえばそうだし、同時期に共通したテーマの作品がかかれば「どっちも黒人の話らしいけど、作品賞なんだからこっちにしとくか」と「グリーンブック」に客が流れるのもわかる。だけれども、どんな理由にせよ、傑作と呼ぶにやぶさかではない作品が埋もれてしまうのは、ちょっともったいないなと思うのだ。
本作は映画自体のデキもさることながら、配給側のやり方もウェルメイドで、例えば公式サイトも悪くない。ファーストビューにはサントラのSpotifyリンクが貼られ、スクロールするとキャストや制作陣のインタビュー動画が観られるようになっている。もちろん、予算の問題もあるだろうし、デザインにも心許ない面があるが、作りもゴテゴテしていない。また、観測した範囲では、どこぞの受賞作のようにバカみたいなキャッチコピーをつけて煽らないなど、とても好感がもてる。
そして何より、タイトルが素晴らしい。本作の原題は「If Beale Street Could Talk」で、ジェームス・ボールドウィンの同名小説が原作である。二人と同じような思いをした無数の「恋人たち」の存在を感じさせるであろう良タイトルだ。
ニコラス・ブリテルとクラシックスが生み出すグルーヴと、知的な抑制
冒頭でも少し触れたが、本作は投獄されたアロンゾ・ファニー・ハント( ステファン・ジェームズ)と、彼を助けるべく奮闘するクレメンタイン・ティッシュ・リヴァーズ(キキ・レイン)を主人公として物語が展開していく。
ファニーとティッシュは幼馴染で、2人が恋に落ちていく過程や初体験の様子、逮捕されてしまうまでの経緯などをティッシュが回想する形で語られ、ファニーを助けるための行動と、妊娠から出産の後までが現実時間として描かれる。容疑を晴らすために戦うのは彼女だけではない。両家の両親(ファニーの母除く)や白人弁護士もまた、彼を開放すべく尽力する。

出典:IMDb
さらに短く、1行で説明するのなら「無実の罪で投獄されてしまった恋人を助けようとする」という単純明快な話であり、誤解を恐れずに書くならば「ありがちな」ストーリーであるとも言える。そこに1970年代、黒人差別、白人至上主義などのレイヤーが重なるわけだが、これとて覆い焼きのように使い古されたレイヤーである。しかし、バリー・ジェンキンスの手腕により、設定に付着した手垢は綺麗に落とされて磨かれ、鈍くも美しい光を放つ。
その光の一端を担うのが、前述したテンポであるのは言うまでもない。劇中では、ニーナ・シモン、アル・グリーン、ビリー・プレストン、ジョン・コルトレーン・クインテットからマイルス・デイヴィスまで、クラシックスがターンテーブルの針などを通して過不足なく鳴らされるが、その対極に位置するのが「ムーンライト」でも劇伴を担当したニコラス・ブリテルによる荘厳なまでの楽曲である。
前半部では、主に回想シーンはニコラスによるスコアが、現実時間では既存楽曲が鳴らされるが、その配分によって見事なまでの緩急、というかグルーヴを生み出している。このリズムの「揺らぎ」は、まさに「ムーンライト」の水泳シーンのようなもので、物語の泳ぎ方をガイドしてくれるとともに「ゆったりとしたテンポなのにダルさを感じさせない」という凄まじい効果をあげている。
リズムもメロディも最高、つまり演奏がパーフェクトである黒人たちの音楽を使いながらも、絶頂には決してもっていかせないといった知的な「抑制」なんて、なかなかできるものではない。というか、抑制しても出てしまう。ニーナ・シモンの『That’s All I Ask』なんて流したら、どんな使い方をしたとしても楽曲の力だけでもっていけてしまうだろう。だが、物語はニーナに登場人物の心情を歌わせこそするが、バリー・ジェンキンスは盛り上げすぎず、ある意味「静かに」鳴らしてみせる。
本作は、黒人を聖人や天使として扱わない
この「抑制」は、楽曲以外にも凄まじい強度で張り巡らされている。もっとも顕著なのは黒人の描き方で、黒人を聖人や天使として扱ってしまう状況に陥っていない。遠い異国の日本でも、さすがに昔、黒人は奴隷として扱われていてさまざまな受難の歴史があったくらいのことは誰でも知っていると思うし、本国ならば尚更である。だが、それを「もうわかってんでしょ、そのくらい」と敢えて描かないというのは相当な胆力であるし、ある意味で「黒人が出てくる映画」で使える、一撃必殺の銃(比喩です。念のため)を抜かないというのもこれまた凄い。

出典:IMDb
本作においては、黒人同士でもいがみ合うし、「嫌な」黒人も出てくる。その筆頭がファニーの母で「息子が投獄されたのは受難である。祈りによって息子は開放される」と信じて疑わず、息子の彼女と腹の中の生命をなかば「悪魔」であると言わんばかりに非難し、挙句の果てに旦那によって沢田研二ばりのビンタを張られ、一撃で物語から退場することで観客は溜飲を下げるが、それとて安易に責めることはできない。彼女には彼女なりの理由と信仰があるからである。
そして、真っ当な人間であるはずの父親同士も「白人の金は俺たちから奪ったものだ(だから盗み返すのは正当な権利である)」と波止場の積荷を盗み、裁判費用を工面する。彼らにもまた、彼らなりの理由がある。とはいえ立派な犯罪だが。それはさておき、全編を通して黒人を「いいモン」としては扱わない。一人の人間として扱う。
「一番悪い奴は、言わなくても(登場させなくても)わかる」かのように、白人様の所業は伝聞でしか描かれない。いくつかの例外はあるが、最も目立つのは白人警官であるベル巡査(エド・スクライン)である。ティッシュに絡んできた白人とファニーが揉み合いをしていると、警ら中のベルがやってくる。その目つきや身のこなし、話し方、恐ろしさは「デトロイト」で悪徳白人警官クラウスを演じたウィル・ポールターの狂気を、たった数分で凌駕してみせる。
では、本作は差別にまみれた、暗いだけの映画なのか?
本作は「観たら暗い気持ちになる映画なのか?」と言われれば、まったくそうではない。もちろん暗い気持ちにもなるが、それ以上に愛や希望に満ちていると書くとバカみたいだが、本当なんだからしょうがない。
ラストシーンの描写は「ティッシュや家族たちの行動、そしてファニーのその後がどうなるのか」といったクリティカルなネタバレになってしまうので省くが、筆者は希望に溢れた結末だと捉える。二人のラブラブっぷりが描かれる回想シーンも暗さを払拭させる。無論、現状を思うと悲しくなってはしまうが、「ムーンライト組」のジャームズ・ラクストン印の映像は、彼らの悲劇ですら美しく描き出す。

出典:IMDb
その映像美が極限まで発揮されているのが、ティッシュの職場であるデパートの香水売り場で、唯一の黒人店員である彼女はペイズリーのワンピースを着てカウンターで接客をする。彼女の周囲にはペールトーンの調度品やパッケージが溢れ、店のロゴが刻印された看板の黒が全体を引き締める。筆者の知っている限りでは「暗殺」の京城三越店に匹敵する、完璧なデパートの映像である。このシーンを観るだけでも1,800円の価値がある。
そして、登場人物たちのリアルさも暗さを払拭するのに一役買う。ファニーを助けようとするファミリーは、打ちのめされているはずであるのに気丈に振る舞う。新しい命が宿ったときには、酒を飲み、レコードに針を落とし、踊る。想像もつかない喪失の只中であるはずなのに、冗談を飛ばし、笑顔で会話をする。
かつて「バックコーラスの歌姫たち」でダーレン・ラヴたちが「最近コーラスの仕事ある?」「ないわよ!」なんて笑いながら話していたように、辛いことがあっても底抜けの明るさで日々を生きる人々の美しさは、痛いほどまでにリアルである。
要は不必要に泣かせないという点に関して、あまりにスマートで、洒脱ですらある。だからこそ、根底に流れる激しい怒りや憎しみが恐ろしいほどに伝わってくる。
白人による黒人に対する仕打ちを、映像内でもっと描き出すこともできるだろうが、バリー・ジェンキンスは鉄壁の抑制でもってそれをしない。しかし、ファニーの片目を充血させるなど、細かいところで「何かがあったこと」を「見せずに」伝えてくる。この「見せない」ことは最大限の効果を発揮し、さらに「見せる」シーンでは爆発力を増す。
「何かがあったこと」というのは「何かがあったのだが、詳しくはわからないこと」である。そしてそれは、結果として「なかったこと」にされる。徹底的に「見せない」ことで雄弁に語らせる本作は、静かで、優しく、美しく、そして底なしの怒りに満ちた、恐るべき傑作である。
—
このコラムについてみんなで語り合えるオンラインコミュニティ「街クリ映画部」会員募集中です。また、コラムの新着情報をオリジナルの編集後記とともにLINE@で無料配信中です。こちらから「友だち追加」をお願い致します。
[イラスト]ダニエル