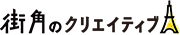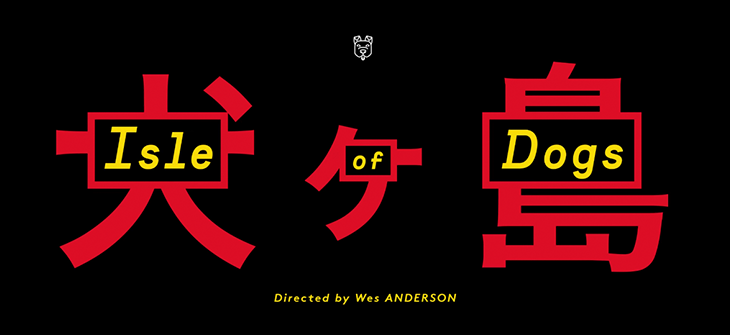出典:公式サイト
「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」は、女子テニス世界チャンピオンのビリー・ジーン・キング(エマ・ストーン)と、元男子チャンピオンであり伝説的なプレイヤー、ボビー・リッグス(スティーブ・カレル)の戦いを描いた映画だ。
当時のテニス業界は昨今のハリウッドでのギャラ男女差問題と同じく、女子テニスプレイヤーの賞金はかなり低く設定されていた。ビリー・ジーンと仲間たちは女子テニス協会を立ち上げ、自らの、そして女性の権利を勝ち取るべく行動する。
というのが、よく語られる本作のあらすじである。
まずは上記と合わせて予告編を見て欲しい。
Reference:YouTube
この試合のバックグラウンドを知っている方を除いては、多くの人が以下のような感想を抱くのではないだろうか。
・本作はテニスの映画である。
・登場する男どもは、女性を下に見ていて嫌な感じだ。
・差別されていた女性が自分たちの権利を勝ち取る物語なのだろう。
・LGBTQの問題も入っていそうだ。
・ああ、今流行りのミートゥーみたいなやつね。
・まあ男性至上主義者の男を、エマ・ストーンが打倒するんだろうな。
もし、予告編で上述したようなことを思って「俺には関係ない映画だ」と思ってリストから外してしまった方には「ぜんぜん違いますよこの映画」と強く訴えたい。
本編を観ればわかるが、予告編はまったく関係ないシーンを繋ぐなど
本作は、こんなバカみたいにわかりやすいマッチメイクではない。最近のフェミニズムだとかミートゥー問題だとかにガッチリとフォーカスをあてた映画でもない。もちろん、ウーマン・リブを鏑矢として、男女平等が叫ばれた時代ではあるので多分に要素は含まれているが、それが全てではない。
 出典:IMDb
出典:IMDb
興行収入を上げたいとか、最近のミートゥー運動などに便乗して「強い女性」を全面に押し出そうとか、制作会社が思ったのかどうかは知らないが、意識的であれ無意識的であれ「こうすれば皆興味もつでしょ、喜ぶでしょ、面白そうでしょ」的なスタンスが表出してしまっている。
史実をもとにした、ある意味ドキュメンタリータッチともとれる映画で公式が、
映画の話をするのに予告編を持ち出すのはバカみたいだが、観客のリテラシーを低く見積もりすぎじゃないのか。何なら「この映画に出てくる男性は、みーんなこんなにクソで、今なら即炎上しそうなほどのバカなんですよ」と、男性を差別しているようにも感じる。
 出典:IMDb
出典:IMDb
そしてこの予告編は、本作のパンフレットが素晴らしいことにより更にクソさを増す。
パンフレットではしっかりと時代背景を説明し、監督並びに主演の2人、そして元プロテニスプレイヤーの杉山愛に的確なインタビューをとっている。
レビューではテニス雑誌「スマッシュ」の編集長である保坂明美氏のテクニカル面の解説や、映画・音楽ジャーナリストの宇野維正氏による当時のタバコ文化とスポンサードなどについて書かれた解説がとても面白く、本作をガッチリと補強する。
以下、なぜ予告編がこんなことになってしまったのかをさらに考察していきたいのだが、楽しくなさそうなのでやめる。
ではどうするか? 女性の権利が
なので、「この映画に出てくる男性は、みーんなこんなにクソで、今なら即炎上しそうなほどのバカなんですよ」と差別された野郎どもの肩を持つことにする。女性の強さばかり騒ぎ立てられて、男性がとりあげられないのは不平等だ。
「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」は、一人の男が見事にカムバックを果たす話である
「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」は、一人の男が大舞台にカムバックを果たす物語である。男の名は元テニス世界チャンピオンのボビー・リッグス。
彼は伝説的なテニスプレイヤーであるが、55歳という年齢もあり、表舞台から姿を消していた。
ボビーはギャンブル依存症のハスラーで、依存症の会合に出かけたり、精神科医のお世話になっているが一向に治る気配がない。というか、治す気がない。
ある日、仲間内での賭けテニスでせしめたロールスロイスを妻に発見され、家を追い出されることとなる。
が、悪いのはギャンブル癖だけで家庭内暴力なんぞしないし、部屋には奥さんの肖像画を飾り、子どもにも愛情を注いでいるいい父親だ。奥さんに至っては、愛を通り越して依存に近い症状すら感じさせる。
 出典:IMDb
出典:IMDb
虚栄心の強い有名人が一番恐れることは何か、世間から忘れ去られることである。ボビーは「俺は元世界チャンピオンだ」と強がりながらも、「ボビー・リッグスが消えていく」世界を過ごしていた。
そんなある日、ビリー・ジーン・キングが旗揚げしたWTA(女子テニス協会)を利用して、カムバックする策を思いつく。「男性至上主義のブタVSモジャ脚のフェミニスト」という、世間的にもテニス業界的にもタイムリーな興行である。
一旦はビリー・ジーンに断られるものの、同じくWTAに所属するマーガレット・スミス・コート(ジェシカ・マクナミー)を説き伏せ、試合では圧勝する。
「男性至上主義のブタ」を自称する彼は、ことあるごとに女性を、女性テニスプレイヤーをバカにする発言を続け、とうとうビリー・ジーンを引きずり出すことに成功する。
世紀の一戦、再び大舞台にカムバックを果たしたボビーを見守るのは、全世界で9,000万人の観客。かくして「The Battle Of The Sexes(性別間の戦い)」が幕を開ける。
 出典:IMDb
出典:IMDb
映画を観ればわかるが、ボビーは決して男性至上主義者ではない。
むしろ、テニス協会をなかば強引に脱会させられたビリー・ジーンたちを(目的のためとはいえ)フックアップし、男子の8分の1であった賞金を遥かに引き上げ、全世界の注目を集めるほどの興行をぶち上げ、自身は差別主義者というヒールに徹することで、結果としてウーマン・リブを強烈に後押ししている。もしかしたら、このオッサンがいちばんの功績者ではないだろうか。
しかも、彼は自分が今、何をやっているかを把握している。おそらく、他人にどう思われているかもよくわかっている。自分が作り上げてきた「ボビー・リッグス」に潰されそうになりながら、必死でハスラーを演じている。
名声や金がある間は人間扱いをしてもらえる。ちやほやしてもらえる。それがなくなったときのことを考えると恐ろしい。全世界の女性を敵に回しても、それが「恐ろしい道だ」とわかっていても、ボビーは自分を止めることができない。
だから本作は、ビリー・ジーン・キングの伝記的映画であるとともに、ボビー・リッグスが幸か不幸かは別としてカムバックを果たす物語でもあるのだ。これを強調しないのは不平等というものであろう。
と、書くと凄い奴に見えそうなのだが、やっぱりどこかバカで、根っからの善人ではない。それが彼の魅力をより引き立てる。何より、複雑な役柄を演じきったスティーヴ・カレルのスキルたるや、とんでもない。
不平等な時代を描いた、平等な映画
いっぽうのビリー・ジーン陣営も「差別だ」などと騒ぎたてるわけでもなく、自分たちの力で権利を勝ち取ろうと奮闘する。
テニス協会を脱退し、スポンサーを見つけ、チケットを手売りしながら全米をドサ回りする。この時代に女性だけの団体が、男性社会と対等に渡り合うのがどれだけ大変なことかは想像の域を出ないが、ジーンたちは決して嘆かず、一生懸命に仕事をこなしていく。
 出典:IMDb
出典:IMDb
決して理不尽に権利を要求しないし、平等にしろなどとは叫ばない。自分たちの行動や力で認めさせようと努力する。
これ、今の時代となっては仕事でも何でも同じで、この、行動しなければ何も変わらない。声を出して叫んでいるだけの奴等は何も得られない。という教訓は、女性の権利だけでなく、すべての問題にあてはめることができる。
本作はビリー・ジーン陣営とボビー・リッグスが、それぞれの問題を抱えながら交錯していく。その問題には優劣なんてない。重さの違いはあれども、みんな平等に悩みながら生きているのである。
不平等な時代を描いた、平等な映画だからこそ、「差別する男性VS差別される女性」という雑なマッチメイクで宣伝して欲しくなかった。
ブルー・スウェード・シューズを履くのは誰か?
平等といえば、最終決戦「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」に向かう前、彼女の履いた靴に少しだけ触れる場面がある。ある人物が登場して話題が変わってしまうため、ほんの一瞬なのだが、彼女が履いていたのは、アディダスの青い靴で「ブルー・スウェード・シューズ」である。
 出典:IMDb
出典:IMDb
この話題も少しだけ触れられるが、「ブルー・スウェード・シューズ」はカール・パーキンスが1956年に発表した楽曲で、今となってはエルビス・プレスリーがカヴァーしたことで広く知られている。雑に意訳すると
ひとつは金のため
ふたつはショーのため
みっつで用意して、さあ始めようぜ
だけどな、お前が何をしてもいいけど、俺のブルー・スウェード・シューズだけは踏むんじゃねえよ
といったことが歌われているが、これはビリー・ジーンの心情でもあり、実はボビー・リッグスの心情でもあると私は考える。歌詞はこう続く。
俺を殴ってもいいぜ
顔を踏んづけたっていい
俺のことを悪く言ったって構わないさ
だけどな、この俺の新品のブルー・スウェード・シューズだけは踏むんじゃねえよ
ブルー・スウェード・シューズは、言い換えれば「尊厳」みたいなもんである。結局、ブルー・スウェード・シューズを履くのは「キング」であるビリー・ジーンだが、ボビーもまた、ペテンでコートしたブルー・スウェード・シューズを履いているのだ。
ここでもまた、映画は男女を平等に扱う。
何度だって言うが、「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」は、「差別する男性VS差別される女性」という、アホみたいなマッチメイクを描いた物語ではない。
念のために書くが、もちろん、そういう見方をするのは自由だ。ボビーに対していくらキレたっていい。私はあなたのブルー・スウェード・シューズを踏むつもりはない。だから、俺のブルー・スウェード・シューズにも近づかないでね。
そんなわけで、「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」は、傑作ではないけれど、実録モノのなかでもなかなかの佳作だと思います。「面白そうだけど、最近ありがちな女性が強いだけの映画はちょっと・・・」と観るのを躊躇している人も、観て損はないと思いますよ。