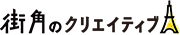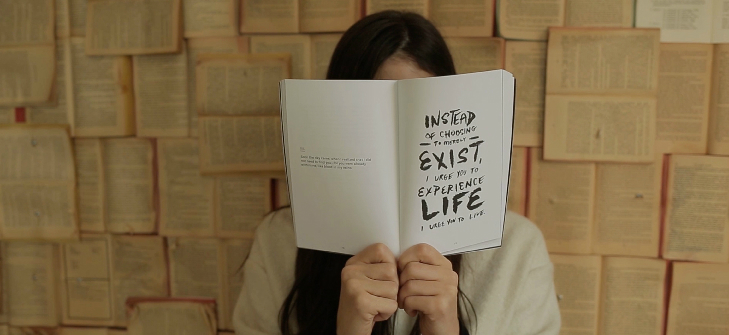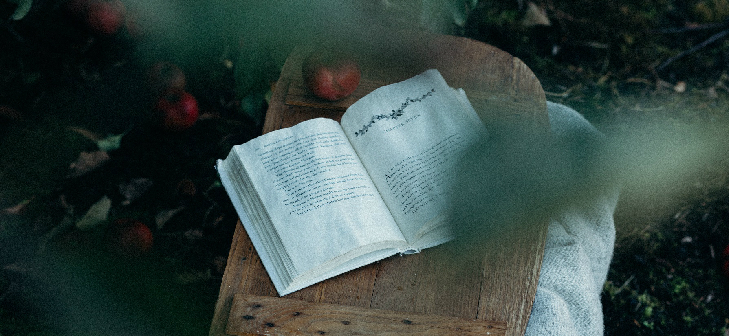私たちの心は、言葉によってできている。
2017年7月19日、第157回芥川賞・直木賞の受賞作が発表された。芥川賞選評の際、とある選考委員が「対岸の火事」という一言を放って物議を醸したが、昨年の下半期に世に出た新作小説は奇しくも、「母語」および「異言語」を
今回は、2017年7月1日~12月31日に新たに刊行された小説のうち、越境する言葉たちを紡いだ印象的な7冊を紹介したい。
まずは、ナイジェリアにゆかりの2冊から。
テジュ・コール『オープン・シティ』(2017)新潮社
アメリカ・ミシガン州で生まれ、幼少期をナイジェリアで過ごしたテジュ・コールによる長編小説。コールは、写真家・美術批評家としても活動している。
夕暮れ時のマンハッタンを歩き続ける、若き精神科医。街中で出会う風景は、ナイジェリアでの記憶や、移民たちの語った物語と響き合う。街の風景を描写する散漫な言葉に思えていたものが、ふいに息遣いを得て、ざわめきとともにすっくと立ち上がってくる。優美でありながら、ふつ、ふつ、と途切れる語りはそのまま、マンハッタンという土地に埋め込まれた裂け目である。ひとつらなりの空間に走る人種・民族・言語、個々の過去。
「オープン・シティ」に閉じ込められた境界線を発見することは、胸の痛む作業だが、この語り手が電車に乗っているのでも車を運転しているのでもなく、ただ「歩いている」ことが読者を救う。左右の足を運ぶリズムで近づいて来る越境の予感を、読み手の指先は静かに受け入れるだろう。
チゴズィエ・オビオマ『ぼくらが漁師だったころ』(2017)早川書房
ナイジェリア出身のチゴズィエ・オビオマは長編デビュー作『僕らが漁師だったころ』でいきなりブッカー賞最終候補作となり、アメリカ現代文学界にその名を轟かせた。1990年代のナイジェリアを舞台に、9歳の少年の視点で語られる家族の崩壊の物語だ。川のほとりで出会った狂人が口にした不吉な予言によって、アグウ家が分解していく様が描かれる。
アグウ家の人々は家庭内では主にイボ語を話す。しかし、子供たちが現地の友人らとおしゃべりをするのに用いられるのはヨルバ語である。両親は、子供たちをしかる際にしばしば英語を口にする。
イボ語では、壺や水がめのことを「ウドゥ」と呼ぶ。アグウ家の「母さん」は、子供たちにこんな風に語り掛ける。
「小川に行くときは」と母さんはかすれ声で詰まりながら切り出した。「必ずウドゥを持って行く。そして小川に屈み込んで、ウドゥいっぱいに水を汲む。それから歩いて―—」
(中略)
「そう、あんたたちはウドゥから漏れ出してしまった。ウドゥにしっかり入れて運んでいた、わたしの人生はあんたたちで満ちていた、そう思っていたのに」
引用:チゴズィエ・オビオマ『ぼくらが漁師だったころ』(2017)早川書房、p.125
チグリス川しかり、黄河しかり、文明や文化は川のほとりで発生するという世界観があるように、水はわたしたちの命(life)の保証である。「母さん」が話すイボ語のウドゥからこぼれ落ちた水は、「ひとつの文化」「ひとつの言語」という水がめで扱おうとすると取りこぼされてしまう人生(life)を示す。
川を渡る。越境する。次は、そうした行為を「暗闇」という装置を用いて浮かび上がらせた作品を紹介しよう。