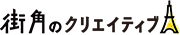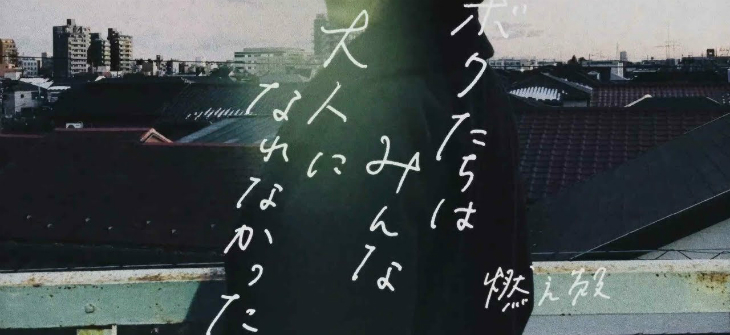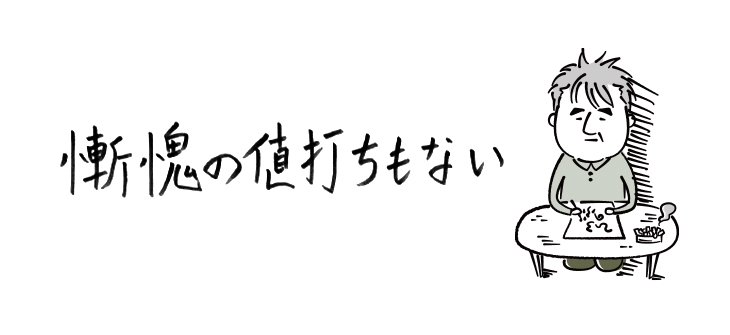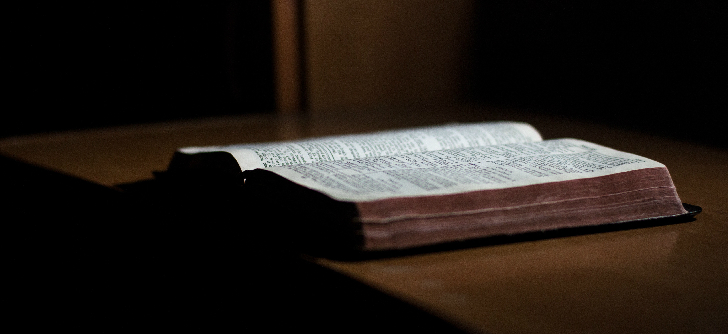
ジム・クレイス『死んでいる』(2004)白水社
最後に紹介するのは、英国の作家ジム・クレイスが書いた観念的な作品だ。死とは結局なんなのか? 体験に先立って、考える余地は多くありそうだ。
動物学者の夫婦が砂丘で撲殺された。主人公はこの、既に死んでいる2人の男女――あるいは、2人が迎えた、死の瞬間そのもの―—である。彼らが死を迎えるまでの数分間、こと切れた直後、死体が腐乱していく様子・・・。分断された時間の中で、この男女は「死んでいる」ことを軸として実に多彩な表情を見せる。彼らを見つめる筆の温度は、低い。
死体はただちに発見された。まず、一匹の甲虫に。続いて、出来立ての傷と尿のにおいに誘われて到着したのは、ヤドリバエとカニの攻撃隊。ふだんはネズミの糞と魚の死肉で間に合わせている連中だ。それから、カモメが一匹。「その夏の午後、砂丘にいたのは死神だけだった」と言い表せたのは、新聞のみだった。引用:ジム・クレイス『死んでいる』(2004)白水社、p.46
肉を分解する虫や鳥、陽の光。こうした存在が「死神」と表現されるとき、死はドラマ性という化粧をぬぐい落とされ、「事件」ではなく「状態」としての素顔を晒す。死を絶対的な地位から引きずり下ろす筆者のまなざしは、我々が物語を生きる存在である以前に、肉体であることを暴きだす。
動物学者として、彼女はわかっているべきだった。草木は過去のすべてを埋めるのだということを、死は吸収されるのだということを。
ジム・クレイス『死んでいる』(2004)白水社、p.185
容赦なく武装解除をさせられた死は、あらゆる変化の一部として輪郭を失っていくかに思われる。結局のところ、死とはなんなのか? 無害化され、他の状態と関連付けることによってしか把握をできないものなのか? 明確な回答は、作品の最後の二文に記されている。このセンテンスを読んだとき、私は死者だけが放つことのできる光について了解し、同時に、できるだけ注意深くその光を目撃するために生きていようかな、と、ぽつんと思った。
以上、死を扱った小説を3冊、ご紹介した。
共に越冬できれば幸いだ。