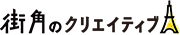『月の満ち欠け』はいわゆる「転生もの」とは一線を画している
本作品は、ひとつの命が繰り返し、いくつもの体の中に宿り、満ちる過程を描いた物語である。こんな風に紹介すると、いかにもキラキラした、運命最高! とでも叫び出しそうな内容を想起させしてしまうかもしれない。だけどそこは佐藤正午。圧倒的な説得力で、「転生もの」への先入観を組み伏せてくれる。
まず、主人公の小山内が、とてつもない現実主義者である。読者からすれば、ぶん殴りたくなるレベルの頭の堅さだ。彼は決定的な場面に立ち会っているときも、「生まれ変わりを信じない」のではなく、「何が起きているのか理解できない」。だから、登場人物の物わかりの良さに支えられた予定調和的なストーリー展開が、1ミリも存在できない。
また、この小説は「転生」によって生じるネガティブな側面にも光を当てる。例えば、性的な問題だ。夭折した人物が生まれ変わって、想い人に再び会えたとして、ランドセルを背負った少女と中年の男性が、一体どのように触れ合うことができるというのか? 事情を知っている周囲の大人はどう振る舞えばいいのだろうか? とてつもなく陰鬱な問題である。でも佐藤正午はガンガン書く。こうした描写が必要以上に重たくならないのは、主人公・小山内が徹底して頑固な、現実主義者であり続けるからだ。
小山内は作品内のあちらこちらで過去に思いを馳せるが、決して、感情をほじくり返して自分で自分を辛くしたりはしない。序盤では「鈍さ」として映った彼の現実主義ぶりは、中盤以降で「強さ」として物語を支える。小山内の「物わかりの悪さ」は、動かぬ現実の象徴として、渦中の人々を冷静に映し出すレンズになる。
ベルナルド・ベルドルッチ監督のオリエンタル三部作のうちの一作品、1990年に公開された映画「シェルタリング・スカイ」のラストシーンでは、月と命を重ね合わせた有名な台詞がある。デブラ・ウィンガー演じる主人公女性のキットに、原作者のポール・ボウルズは「疲れたんだね」と話しかけたあと、こんなセリフを口にする。
人は自分の死を予知できず、人生を尽きせぬ泉だと思う。だが、物事はすべて数回起こるか起こらないかだ。自分の人生を左右したと思えるほど大切な子供の頃の思い出も、あと何回心に思い浮かべるか? せいぜい4、5回思い出すくらいだ。あと何回満月を眺めるか? せいぜい20回だろう。だが人は無限の機会があると思い込んでいる。
引用:「シェルタリング・スカイ」
無限の機会を望みながら、有限の命を生きる私たちは、また次があるさ、などと
生きるということの持つ光と影を、うねるようなリズムの中で描き切った『月の満ち欠け』。月の光に照らされたことがある、全ての人におすすめしたい。